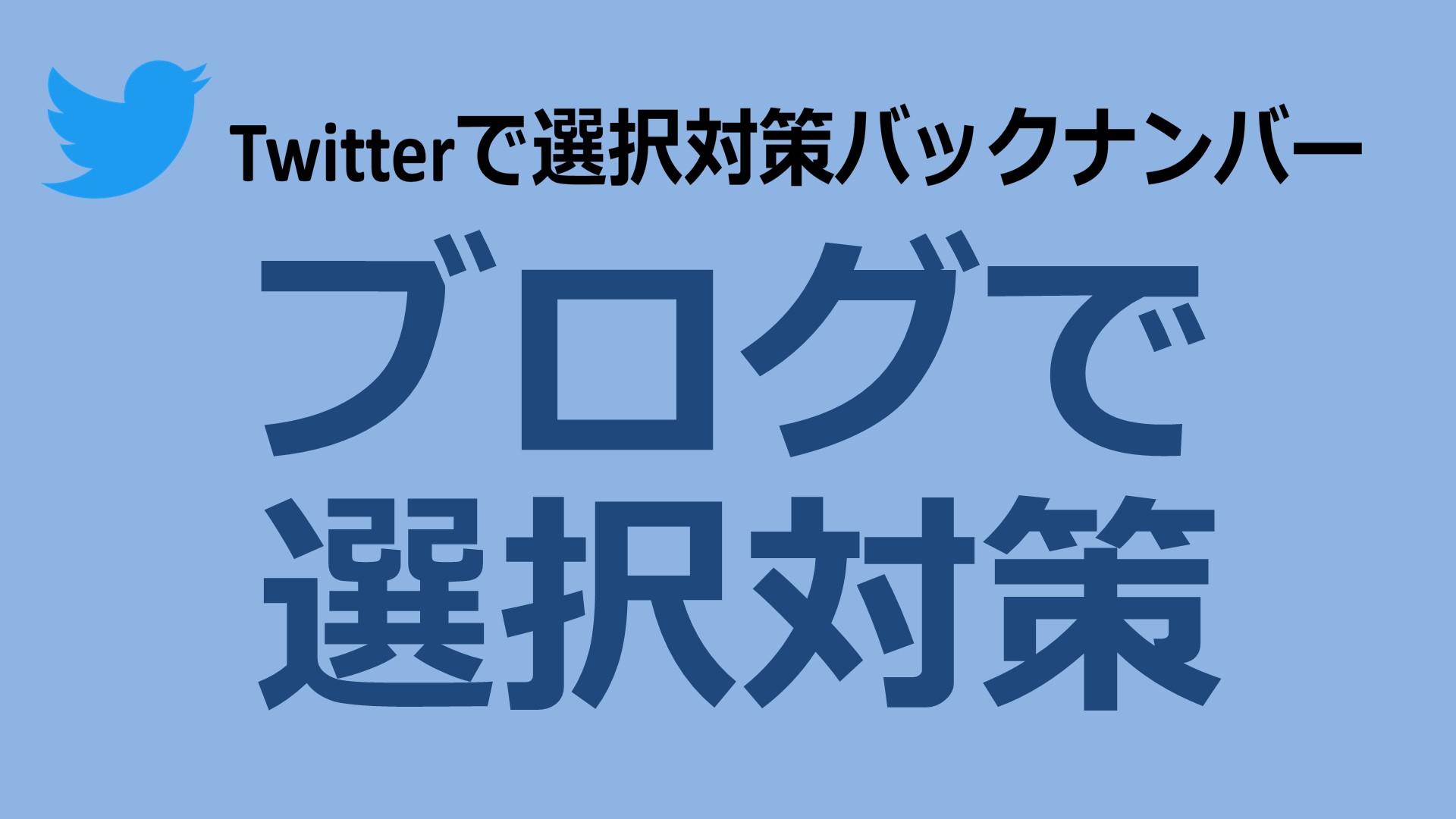皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
時間外・休日労働協定(正解率42%)
問題
時間外・休日労働協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は、【?】であることを要する。
A 45時間未満
B 45時間以下
C 100時間未満
D 100時間以下
このまとめサイト内の判例から、毎年出題されているのも事実。 1日1つずつ確認するだけで、試験までに多くの判例を知ることができる。 多くの判例を知れば、未知の判例への対応力も上がる。 より詳しく知りたい時は事件名でググってみよう。
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「C 100時間未満」。
限度時間は”3つ”の天井。
①時間外が月45時間以下
②(特別条項)時間外+休日が月100時間未満
③(36協定の範囲内であっても超えてはいけない)時間外+休日が月100時間未満
「時間外・休日労働協定で定めるところによって~労働させる場合であっても」は③を指す表現。
①の上限は「時間外労働」のみに適用され、「休日労働」には適用がないため、例えば時間外45h+休日労働60hも適法になってしまう。
そこで、③の上限を設け、時間外+休日労働あわせて100h(過労死認定基準)以上とならないようにしている。
ほか、かんたんな見分け方としては、「時間外のみなら45、時間外と休日なら100」というのもある。
以上、今回の問題でした。
関連論点- いわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合、届出によって協定の効力は発生するため、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。
- 本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。
- 協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。
- 労使当事者は、労働基準法第36条第1項の時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。
- 1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、実労働時間は8時間であるので、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
- 労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・直律的効力〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117条以下〕の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者にも及ぶ。
- 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。
- 最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする、とされている。
- 労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない(民事上の義務は、就業規則や労働契約といった契約上の根拠になるものから生じる)。
「労使協定と就業規則の違いがよく分からない&」「労使協定から民事上の義務は生じないってどういうこと?」という疑問をお持ちの方はぜひ御覧ください。担当講師:金沢博憲(#社労士24、経験者合格コース)経験者合格コースの詳細https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_de...
- 36協定においては、対象期間を定めるものとされているが、当該対象期間は、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとされている。また、当該対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数についても定めなければならない。
- 労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。
- 小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることはできない(1月90時間、2月70時間、3月85時間の3か月平均が80時間超えているため)。
- 変形労働時間制により労働させる場合においては、有害業務については、1日について労働時間が10時間と定められた日は、12時間まで労働させることができる。
- 坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。
- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であれば本条に抵触しない(その日における坑内労働等の労働時間数が1日についての法定労働時間数に2時間を加えて得た時間数をこえないときは、法第36条第1項本文の手続きがとられている限り適法であるため)。
毎日判例
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「一問一答15,000回で合格レベル」
ゆで理論風解説。
・過去問は10年分が主流。
・1年350肢で3,500肢。
・珍問や廃止規定の問題をざっくり省いて3,000肢。
・定着に最低5回転は必要。
3,000肢×5回=15,000回。
~15,000問への挑戦~
「択一式トレ問進捗表β版(公開用)EXCEL版」
・手作り感満載
・クリックするとDL開始
・着手日と問題数を入力
・科目毎の「問題数」「15000への進捗率」「直近との間隔」「最大間隔の科目」が表示
・保護解除でカスタマイズ可能
↓ ↓ ↓
ここをクリックするとダウンロード開始
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。