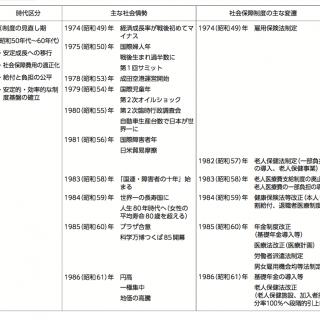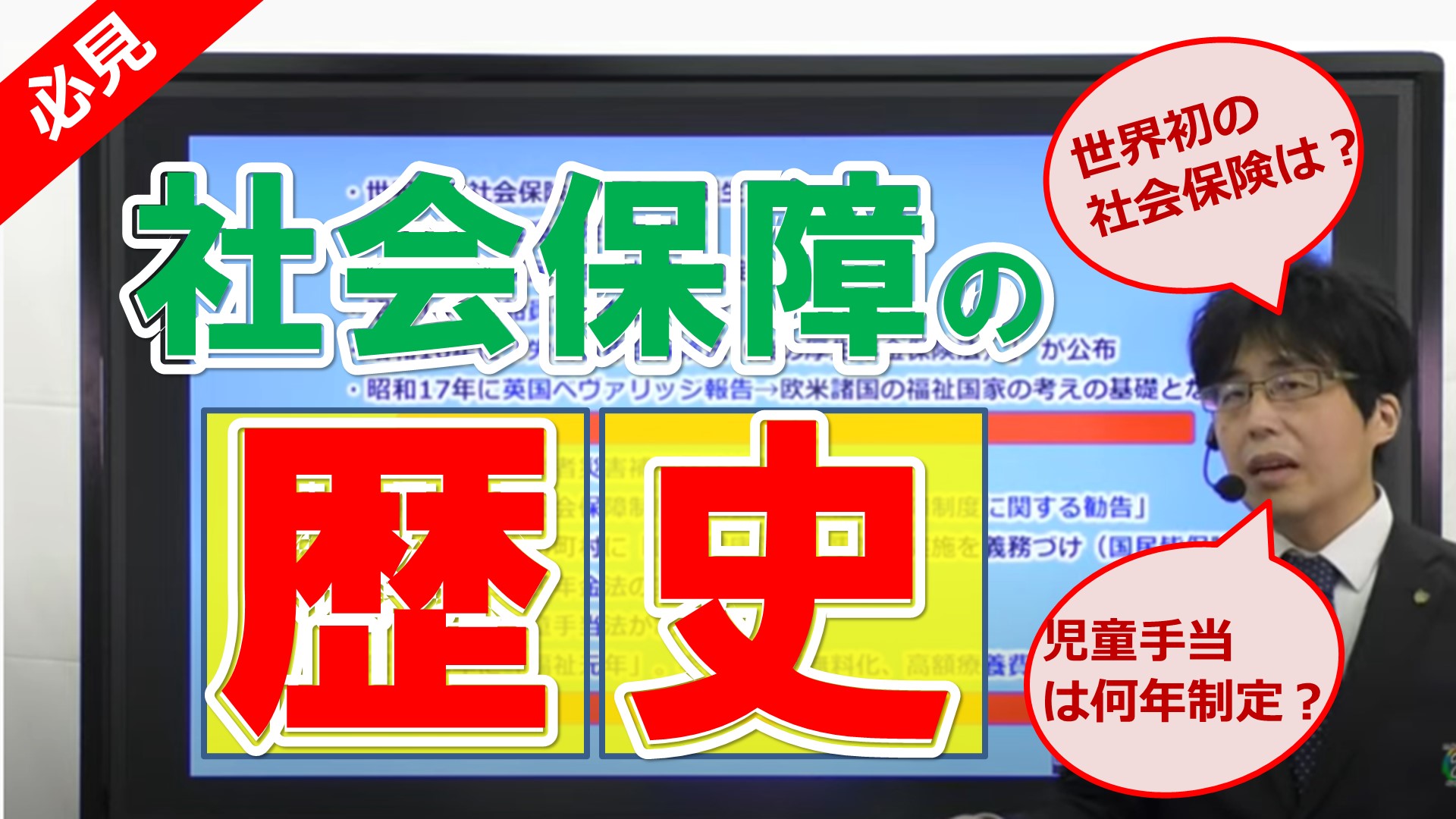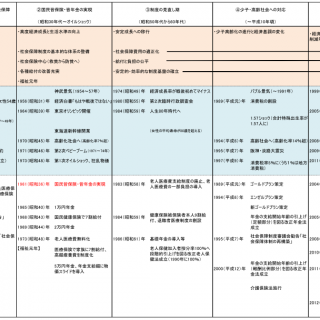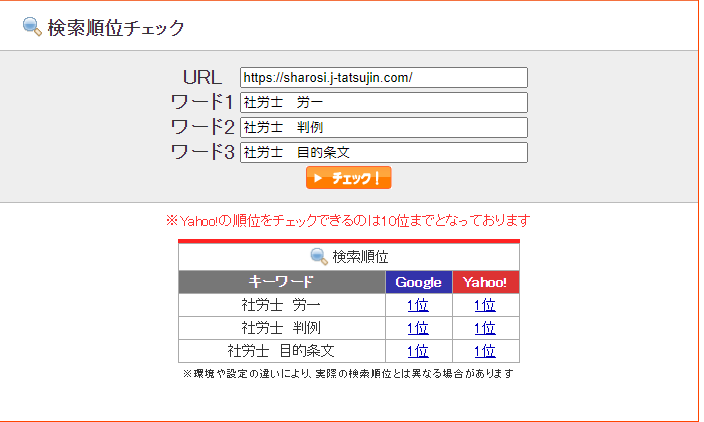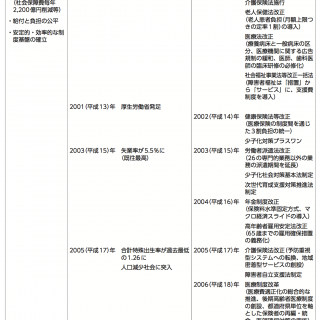みなさん、こんにちは。
金沢博憲(社労士24)です。
10月15日に判決が出た「日本郵便事件」の概要と争点についてです。
年末年始勤務手当、病気休暇,夏期・冬季休暇、扶養手当などについて争われています。
なお、13日には、同じく正規・非正規間の待遇格差(賞与・退職金の支給の有無)の合理性について争われた裁判の判決が2つ出されています。
そして15日、最高裁は、正社員と契約社員の間にある「年末年始の勤務手当、病気休暇、夏期休暇・冬期休暇、祝日給、扶養手当に係る労働条件の相違について、不合理な格差」という判断を示しました。
日本郵便格差訴訟①
事件の概要
本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して勤務している第1審原告らが,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している労働者(正社員)と第1審原告らとの間で,年末年始勤務手当,病気休暇,夏期休暇及び冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反するものであったと主張して,第1審被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償を求めるなどの請求をする事案である。
原判決及び争点
原判決(東京高裁)は,①年末年始勤務手当の支給の有無及び私傷病による病気休暇を有給とするか無給とするかに関する労働条件の相違について,いずれも労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たるとして,これらに係る損害賠償請求の一部を認容し,②夏期休暇及び冬期休暇の付与の有無に関する労働条件の相違について,同条にいう不合理と認められるものに当たるとした上で,第1審原告らにこれによる損害が生じたとはいえないとして,これに係る損害賠償請求を棄却した。
日本郵便格差訴訟②
事件の概要
本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して勤務し,又は勤務していた第1審原告らが,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している労働者(正社員)と第1審原告らとの間で,年末年始勤務手当,祝日給,扶養手当,夏期休暇及び冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反するものであったと主張して,第1審被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償を求めるなどの請求をする事案である。
原判決及び争点
原判決(大阪高裁)は,①年末年始勤務手当及び年始期間(祝日を除く1月1日~3日)の勤務に対する祝日給の支給の有無に関する労働条件の相違について,有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超えていた時期に限り,労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たるとして,損害賠償請求の一部を認容し,②扶養手当の支給の有無に関する労働条件の相違について,同条にいう不合理と認められるものに当たらないとして,損害賠償請求を棄却し,③夏期休暇及び冬期休暇の付与の有無に関する労働条件の相違について,同条にいう不合理と認められるものに当たることを前提に,第1審原告らに上記の休暇の日数分の賃金に相当する額の損害が発生したとして,損害賠償請求を認容した。
本件における争点は,上記①及び②につき,労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たるか否か,上記③につき,損害が生じたといえるか否かである。
最高裁の判決
15日、最高裁は、正社員と契約社員の間にある「年末年始の勤務手当、病気休暇、お盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、扶養手当に係る労働条件の相違について、不合理な格差」という判断を示しました。
詳細は判決文をみてからですね。
年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれらを支給しないという労働条件の相違がそれぞれ労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされました。
年末年始勤務手当
まず、年末年始勤務手当について考察します。
その性質・目的は
|
・最繁忙期であり,多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において,同業務に従事したことに対し,その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有する |
としています。
そして
| ・職務の内容→相違がある(時給制契約社員は,特定の業務のみに従事し,各事務について幅広く従事することは想定されておらず,昇任や昇格は予定されていない) ・変更の範囲→相違がある(時給制契約社員は,職場及び職務内容を限定して採用されており,正社員のような人事異動は行われない) ・その他の事情→正社員登用制度がある |
という事情があると評価しています。
その上で、
| 年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば,これを支給することとした趣旨は,郵便の業務を担当する時給制契約社員にも妥当するものである。そうすると,郵便の業務を担当する正社員と上記時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができる |
と”不合理”判定の判断しています。
つまり、年末年始勤務手当の趣旨は、「多くの労働者が休日として過ごしている期間において,同業務に従事したことに対し,その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価」であるため、「職務の内容等につき相応の相違がある」としても、正社員と同じく年末年始に実際に勤務した契約社員に支給がないのは不合理、という判断です。
「職務の内容等につき相応の相違があるとしても不合理」というのが、ポイントです。
一連の判決では、メトロ、大阪医科大、日本郵便のいずれも「職務内容等には相違がある」としています。
それでも結論が分かれたのは「待遇ごとの趣旨」の違いです。
年末年始手当は「年末年始に勤務する」という”行為”が支給要件であるため、同じ”行為”をした契約社員に支給がないのは不合理、という展開です。
一方、退職金と賞与は、「正社員の定着目的」、突き詰めると「正社員(相当)であること」という”身分”を支給要件と評価しています。従って、正社員と職務内容等が同一でない限りは、契約社員に支給がないことは不合理とまではいえない、という展開になっています。
年始期間の勤務に対する祝日給
次に、祝日給について考察します。
その性質・目的は
| ・年始期間については,郵便の業務を担当する正社員に対して特別休暇が与えられており,これは,多くの労働者にとって年始期間が休日とされているという慣行に沿った休暇を設けるという目的によるもの ・年始期間の勤務に対する祝日給は,特別休暇が与えられることとされているにもかかわらず最繁忙期であるために年始期間に勤務したことについて,その代償として,通常の勤務に対する賃金に所定の割増しをしたものを支給することとされたもの |
その上で
| ・職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,上記祝日給を正社員に支給する一方で本件契約社員にはこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができる |
という”不合理”判断しています。
つまり、年始期間の勤務に対する祝日給は、「年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨」であるため、「職務の内容等につき相応の相違がある」としても、同じく年始に勤務した契約社員に支給がないのは不合理、という判断です。
やはり「職務の内容等につき相応の相違があるとしても不合理」というのが、ポイントです。
扶養手当
次に、扶養手当について考察します。
その性質・目的は
|
・正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから,その生活保障や福利厚生を図り,扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的 |
としています。
その上で、
| 職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に扶養手当に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができる |
という”不合理”判断しています。
つまり、扶養手当の支給の趣旨は、「正社員には長く働いてもらうことを期待しているから、扶養親族がある者の生活に余裕を持たせることで、長く働いてもらう目的」であるため、「職務の内容等につき相応の相違がある」としても、扶養親族があり,かつ,相応に継続的な勤務が見込まれる契約社員に支給がないのは不合理、という判断です。
やはり「職務の内容等につき相応の相違があるとしても不合理」というのが、ポイントです。
第1 事案の概要
1 本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務し,又は勤務していた時給制契約社員又は月給制契約社員である第1審原告らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と第1審原告らとの間で,年末年始勤務手当,祝日給,扶養手当,夏期休暇及び冬期休暇(以下「夏期冬期休暇」という。)等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をする事案である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ア 第1審被告は,国及び日本郵政公社が行っていた郵便事業を承継した郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の合併により,平成24年10月1日に成立した株式会社であり,郵便局を設置して,郵便の業務,銀行窓口業務,保険窓口業務等を営んでいる。
イ 第1審原告X1を除く第1審原告らは,いずれも,国又は日本郵政公社に有期任用公務員として任用された後,平成19年10月1日,郵便事業株式会社との間で有期労働契約を締結し,同社及び第1審被告との間でその更新を繰り返して,郵便外務事務(配達等の事務)に従事し,又は従事していた時給制契約社員又は月給制契約社員である。このうち,第1審原告X3は,平成24年8月1日に時給制契約社員から月給制契約社員となったが,その余の者は,いずれも時給制契約社員である。また,第1審原告X4は,平成28年3月31日,第1審被告を退職した。
第1審原告X1は,平成22年4月,郵便事業株式会社との間で有期労働契約を締結し,同社及び第1審被告との間で有期労働契約の締結又は更新を繰り返して,郵便外務事務に従事する時給制契約社員である。
(2)ア 第1審被告に雇用される従業員には,無期労働契約を締結する正社員と有期労働契約を締結する期間雇用社員が存在し,それぞれに適用される就業規則及び給与規程は異なる。
イ 正社員に適用される就業規則において,正社員の勤務時間は,1日について原則8時間,4週間について1週平均40時間とされている。 平成26年3月31日以前の人事制度(以下「旧人事制度」という。)において,正社員は,企画職群,一般職群(以下「旧一般職」という。)及び技能職群に区分され,このうち郵便局における郵便の業務を担当していたのは旧一般職であった。
そして,平成26年4月1日以後の人事制度(以下「新人事制度」という。)において,正社員は,管理職,総合職,地域基幹職及び一般職(以下「新一般職」という。)の各コースに区分され,このうち郵便局における郵便の業務を担当するのは地域基幹職及び新一般職である。
ウ 期間雇用社員に適用される就業規則において,期間雇用社員は,スペシャリスト契約社員,エキスパート契約社員,月給制契約社員,時給制契約社員及びアルバイトに区分されており,それぞれ契約期間の長さや賃金の支払方法が異なる。このうち時給制契約社員は,郵便局等での一般的業務に従事し,時給制で給与が支給されるものとして採用された者であって,契約期間は6か月以内で,契約を更新することができ,正規の勤務時間は,1日について8時間以内,4週間について1週平均40時間以内とされている。また,月給制契約社員は,高い知識・能力を発揮して郵便局等での一般的業務に従事し,月給制で給与が支給されるものとして採用された者であって,契約期間は1年以内で,契約を更新することができ,正規の勤務時間は,1日について6時間以上8時間以内,4週間について1週平均40時間,35時間又は30時間とされている。
(3) 正社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する正社員の給与は,基本給と諸手当で構成されている。諸手当には,扶養手当,住居手当,祝日給,特殊勤務手当,夏期手当,年末手当等がある。
このうち扶養手当は,所定の扶養親族のある者に支給されるものであり,その額は,扶養親族の種類等に応じて,扶養親族1人につき月額1500円~1万5800円である。
また,祝日給は,正社員が祝日において割り振られた正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務したとき(祝日代休が指定された場合を除く。)及び祝日を除く1月1日から同月3日までの期間(以下「年始期間」という。)に勤務したときに支給されるものであり,その額は,月の初日から末日までの間における祝日給の支給対象時間(勤務時間)に次の算式により求められる額を乗じて得た額である。なお,正社員に適用される就業規則において,郵便の業務を担当する正社員には,年始期間について特別休暇が与えられるものとされている。
((基本給の月額+基本給及び扶養手当の月額に係る調整手当の月額+隔遠地手当の月額)×12/年間所定勤務時間数)×100分の135
さらに,特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する正社員に,その勤務の特殊性に応じて支給するものとされている。特殊勤務手当の一つである年末年始勤務手当は,12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであり,その額は,12月29日から同月31日までは1日につき4000円,1月1日から同月3日までは1日につき5000円であるが,実際に勤務した時間が4時間以下の場合は,それぞれその半額である。
このほか,正社員に適用される就業規則では,郵便の業務を担当する正社員に夏期冬期休暇が与えられることとされている。夏期休暇は6月1日から9月30日まで,冬期休暇は10月1日から翌年3月31日までの各期間において,それぞれ3日まで与えられる有給休暇である。
(4)ア 期間雇用社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する時給制契約社員の給与は,基本賃金と諸手当で構成されている。諸手当には,祝日割増賃金,特殊勤務手当,臨時手当等がある。 このうち祝日割増賃金は,時給制契約社員が祝日に勤務することを命ぜられて勤務したときに支給されるものであり,その額は,月の初日から末日までの期間における祝日割増賃金の支給対象時間(勤務時間)に,基本賃金額(時給)の100分の35を乗じて得た額である。
イ 期間雇用社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する月給制契約社員の給与は,基本賃金と諸手当で構成されている。諸手当には,祝日割増賃金,特殊勤務手当,臨時手当等がある。 このうち祝日割増賃金は,月給制契約社員が祝日において割り振られた正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務したときに支給されるものであり,その額は,月の初日から末日までの間における祝日割増賃金の支給対象時間(勤務時間)に次の算式により求められる額を乗じて得た額である。
(基本賃金額(月給)×12/年間所定勤務時間数)×100分の135
ウ もっとも,郵便の業務を担当する時給制契約社員及び月給制契約社員(以下,併せて「本件契約社員」という。)に対して,扶養手当及び年末年始勤務手当は支給されず,祝日割増賃金は,正社員に対する祝日給とは異なり,年始期間に勤務したときには支給されない。なお,本件契約社員には年始期間について特別休暇は与えられていない。
また,本件契約社員に対して,夏期冬期休暇は与えられていない。
(5)ア 旧一般職及び地域基幹職は,郵便外務事務,郵便内務事務等に幅広く従事すること,昇任や昇格により役割や職責が大きく変動することが想定されている。他方,新一般職は,郵便外務事務,郵便内務事務等の標準的な業務に従事することが予定されており,昇任や昇格は予定されていない。
また,正社員の人事評価においては,業務の実績そのものに加え,部下の育成指導状況,組織全体に対する貢献等の項目によって業績が評価されるほか,自己研さん,状況把握,論理的思考,チャレンジ志向等の項目によって正社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。
イ これに対し,本件契約社員は,郵便外務事務又は郵便内務事務のうち,特定の業務のみに従事し,上記各事務について幅広く従事することは想定されておらず,昇任や昇格は予定されていない。
また,時給制契約社員の人事評価においては,上司の指示や職場内のルールの遵守等の基本的事項に関する評価が行われるほか,担当する職務の広さとその習熟度についての評価が行われる。月給制契約社員の人事評価においては,業務を適切に遂行していたかなどの観点によって業績が評価されるほか,上司の指示の理解,上司への伝達等の基本的事項や,他の期間雇用社員への助言等の観点により,月給制契約社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。他方,本件契約社員の人事評価においては,正社員とは異なり,組織全体に対する貢献によって業績が評価されること等はない。
(6) 旧一般職を含む正社員には配転が予定されている。ただし,新一般職は,転居を伴わない範囲において人事異動が命ぜられる可能性があるにとどまる。 これに対し,本件契約社員は,職場及び職務内容を限定して採用されており,正社員のような人事異動は行われず,郵便局を移る場合には,個別の同意に基づき,従前の郵便局における雇用契約を終了させた上で,新たに別の郵便局における勤務に関して雇用契約を締結し直している。
(7) 本件契約社員に対しては,正社員に登用される制度が設けられており,人事評価や勤続年数等に関する応募要件を満たす応募者について,適性試験や面接等により選考される。
第2 令和元年(受)第794号上告代理人樋󠄀 口隆明ほかの上告受理申立て理由第2並びに同第795号上告代理人森博行ほかの上告受理申立て理由第2及び第4の2(ただし,いずれも排除されたものを除く。)について
1 原審は,前記第1の2の事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,郵便事業株式会社及び第1審被告との間で更新された有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算雇用期間」という。)が5年を超えていた時期における第1審原告らの年末年始勤務手当及び年始期間の勤務に対する祝日給に係る損害賠償請求の一部を認容すべきものとする一方,第1審原告X1について,通算雇用期間が5年を超えていなかった平成27年4月30日以前の年末年始勤務手当及び同日以前の年始期間の勤務に対する祝日給に係る損害賠償請求を棄却すべきものとした。
(1) 第1審被告における年末年始勤務手当は,年末年始の時期に業務に従事しなければならない正社員の労苦に報いる趣旨で支給されるものであるところ,本件契約社員が原則として短期雇用を前提とすること等からすると,正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で,本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,直ちに労働契約法20条にいう不合理と認められるものには当たらない。もっとも,本件契約社員であっても,通算雇用期間が5年を超える場合には,正社員との間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違を設ける根拠は薄弱なものとならざるを得ず,上記相違は,同条にいう不合理と認められるものに当たる。
(2) 第1審被告において,正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で,本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は,年始期間につき正社員に対してのみ与えられる特別休暇についての相違を反映したものであるところ,長期雇用を前提とする正社員と,原則として短期雇用を前提とする本件契約社員との間で,休暇等について異なる制度や運用を採用することには一定の合理性があるから,上記特別休暇についての相違が直ちに労働契約法20条にいう不合理と認められるものには当たらず,これを反映した上記祝日給についての相違も,同条にいう不合理と認められるものには当たらない。もっとも,本件契約社員であっても,通算雇用期間が5年を超える場合には,上記相違を設ける根拠は薄弱なものとならざるを得ず,上記相違は,同条にいう不合理と認められるものに当たる。
2 しかしながら,原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 年末年始勤務手当について
第1審被告における年末年始勤務手当は,郵便の業務を担当する正社員の給与を構成する特殊勤務手当の一つであり,12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであることからすると,同業務についての最繁忙期であり,多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において,同業務に従事したことに対し,その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有するものであるといえる。また,年末年始勤務手当は,正社員が従事した業務の内容やその難度等に関わらず,所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり,その支給金額も,実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。
上記のような年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば,これを支給することとした趣旨は,本件契約社員にも妥当するものである。そうすると,前記第1の2(5)~(7)のとおり,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で,本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
(2) 年始期間の勤務に対する祝日給について
第1審被告における祝日給は,祝日のほか,年始期間の勤務に対しても支給されるものである。年始期間については,郵便の業務を担当する正社員に対して特別休暇が与えられており,これは,多くの労働者にとって年始期間が休日とされているという慣行に沿った休暇を設けるという目的によるものであると解される。これに対し,本件契約社員に対しては,年始期間についての特別休暇は与えられず,年始期間の勤務に対しても,正社員に支給される祝日給に対応する祝日割増賃金は支給されない。そうすると,年始期間の勤務に対する祝日給は,特別休暇が与えられることとされているにもかかわらず最繁忙期であるために年始期間に勤務したことについて,その代償として,通常の勤務に対する賃金に所定の割増しをしたものを支給することとされたものと解され,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間の祝日給及びこれに対応する祝日割増賃金に係る上記の労働条件の相違は,上記特別休暇に係る労働条件の相違を反映したものと考えられる。
しかしながら,本件契約社員は,契約期間が6か月以内又は1年以内とされており,第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者も存するなど,繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく,業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。そうすると,最繁忙期における労働力の確保の観点から,本件契約社員に対して上記特別休暇を付与しないこと自体には理由があるということはできるものの,年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は,本件契約社員にも妥当するというべきである。そうすると,前記第1の2(5)~(7)のとおり,郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,上記祝日給を正社員に支給する一方で本件契約社員にはこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で,本件契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
3 以上と異なる原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。第1審原告X1の論旨は以上の趣旨をいうものとして理由がある。他方,以上によれば,第1審被告の論旨は採用することができない。
第3 令和元年(受)第795号上告代理人森博行ほかの上告受理申立て理由第7について
(扶養手当)
1 原審は,前記第1の2の事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,第1審原告X2及び第1審原告X3の扶養手当に係る損害賠償請求を棄却した。 第1審被告における扶養手当は,長期雇用を前提として基本給を補完する生活手当としての性質及び趣旨を有するものであるところ,本件契約社員が原則として短期雇用を前提とすること等からすると,正社員に対して扶養手当を支給する一方で,本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらない。
2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
第1審被告において,郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは,上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから,その生活保障や福利厚生を図り,扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。このように,継続的な勤務が見込まれる労働者に扶養手当を支給するものとすることは,使用者の経営判断として尊重し得るものと解される。もっとも,上記目的に照らせば,本件契約社員についても,扶養親族があり,かつ,相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば,扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべきである。そして,第1審被告においては,本件契約社員は,契約期間が6か月以内又は1年以内とされており,第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど,相応に継続的な勤務が見込まれているといえる。そうすると,前記第1の2(5)~(7)のとおり,上記正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に扶養手当に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものというべきである。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支給する一方で,本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
3 以上と異なる原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は以上の趣旨をいうものとして理由がある。
第4 令和元年(受)第794号上告代理人樋󠄀 口隆明ほかの上告受理申立て理由第3の4について
1 原審は,郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で,本件契約社員である第1審原告らに対してこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たることを前提に,上記相違によって夏期冬期休暇の日数分の賃金に相当する額の損害が発生したと判断した。所論は,原審のこの判断には民法709条の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。
2 第1審被告における夏期冬期休暇は,有給休暇として所定の期間内に所定の日数を取得することができるものであるところ,本件契約社員である第1審原告らは,夏期冬期休暇を与えられなかったことにより,当該所定の日数につき,本来する必要のなかった勤務をせざるを得なかったものといえるから,上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたものということができる。
以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
第5 結論
以上のとおりであるから,原判決中,第1審原告X1の平成27年4月30日以前における年末年始勤務手当及び同日以前における年始期間の勤務に対する祝日給に係る損害賠償請求に関する部分並びに第1審原告X2及び第1審原告X3の扶養手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄し,損害額等について更に審理を尽くさせるため,これらの部分につき本件を原審に差し戻すとともに,第1審被告の上告並びに第1審原告X1,第1審原告X2及び第1審原告X3のその余の上告を棄却することとする。なお,その余の上告受理申立て理由は,上告受理の決定において排除された。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山口 厚 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 深山卓也)
私傷病の有給休暇
私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与える一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例です。
私傷病の有給休暇について考察します。
その性質・目的は
|
・正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから,その生活保障を図り,私傷病の療養に専念させることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的 |
としています。
そして
| ・職務の内容→相違がある ・変更の範囲→相違がある ・その他の事情→正社員登用制度がある |
という事情があると評価しています。
その上で、
| 職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,私傷病による病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく,これを有給とするか無給とするかにつき労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができる |
と判断しています。
つまり、私傷病の有給休暇の趣旨は、「私傷病の療養に専念させることを通じて」「継続的な雇用を確保するという目的」であるので、「職務の内容等につき相応の相違がある」としても、「日数につき相違を設けることはともかく」、相応に継続的な勤務が見込まれている契約社員の休暇を無給とするのは不合理、という判断です。
第1 事案の概要
1 本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務している時給制契約社員である第1審原告らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と第1審原告らとの間で,年末年始勤務手当,病気休暇,夏期休暇及び冬期休暇(以下「夏期冬期休暇」という。)等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をする事案である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ア 第1審被告は,国及び日本郵政公社が行っていた郵便事業を承継した郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の合併により,平成24年10月1日に成立した株式会社であり,郵便局を設置して,郵便の業務,銀行窓口業務,保険窓口業務等を営んでいる。
イ 第1審原告X1及び第1審原告X2は,いずれも,国又は日本郵政公社に有期任用公務員として任用された後,平成19年10月1日,郵便事業株式会社との間で有期労働契約を締結し,同社及び第1審被告との間でその更新を繰り返して勤務する時給制契約社員である。また,第1審原告X3は,平成20年10月14日,郵便事業株式会社との間で有期労働契約を締結し,同社及び第1審被告との間でその更新を繰り返して勤務する時給制契約社員である。第1審原告X1及び第1審原告X3は,郵便外務事務(配達等の事務)に従事し,第1審原告X2は,郵便内務事務(窓口業務,区分け作業等の事務)に従事している。
(2)ア 第1審被告に雇用される従業員には,無期労働契約を締結する正社員と有期労働契約を締結する期間雇用社員が存在し,それぞれに適用される就業規則及び給与規程は異なる。
イ 正社員に適用される就業規則において,正社員の勤務時間は,1日について原則8時間,4週間について1週平均40時間とされている。 平成26年3月31日以前の人事制度(以下「旧人事制度」という。)において,正社員は,企画職群,一般職群(以下「旧一般職」という。)及び技能職群に区分され,このうち郵便局における郵便の業務を担当していたのは旧一般職であった。
そして,平成26年4月1日以後の人事制度(以下「新人事制度」という。)において,正社員は,管理職,総合職,地域基幹職及び一般職(以下「新一般職」という。)の各コースに区分され,このうち郵便局における郵便の業務を担当するのは地域基幹職及び新一般職である。
ウ 期間雇用社員に適用される就業規則において,期間雇用社員は,スペシャリスト契約社員,エキスパート契約社員,月給制契約社員,時給制契約社員及びアルバイトに区分されており,それぞれ契約期間の長さや賃金の支払方法が異なる。このうち時給制契約社員は,郵便局等での一般的業務に従事し,時給制で給与が支給されるものとして採用された者であって,契約期間は6か月以内で,契約を更新することができ,正規の勤務時間は,1日について8時間以内,4週間について1週平均40時間以内とされている。
(3) 正社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する正社員の給与は,基本給と諸手当で構成されている。諸手当には住居手当,祝日給,特殊勤務手当,夏期手当,年末手当等がある。このうち特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する正社員に,その勤務の特殊性に応じて支給するものとされている。特殊勤務手当の一つである年末年始勤務手当は,12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであり,その額は,12月29日から同月31日までは1日につき4000円,1月1日から同月3日までは1日につき5000円であるが,実際に勤務した時間が4時間以下の場合は,それぞれその半額である。
また,正社員に適用される就業規則では,郵便の業務を担当する正社員に夏期冬期休暇及び病気休暇が与えられることとされている。夏期休暇は6月1日から9月30日まで,冬期休暇は10月1日から翌年3月31日までの各期間において,それぞれ3日まで与えられる有給休暇である。病気休暇は,私傷病等により,勤務日又は正規の勤務時間中に勤務しない者に与えられる有給休暇であり,私傷病による病気休暇は少なくとも引き続き90日間まで与えられる。
(4) 期間雇用社員に適用され,就業規則の性質を有する給与規程において,郵便の業務を担当する時給制契約社員の給与は,基本賃金と諸手当で構成されている。諸手当には,祝日割増賃金,特殊勤務手当,臨時手当等がある。もっとも,上記時給制契約社員に対して年末年始勤務手当は支給されない。
また,上記時給制契約社員には,夏期冬期休暇が与えられない一方,期間雇用社員に適用される就業規則において,病気休暇が与えられることとされているが,私傷病による病気休暇は1年に10日の範囲で無給の休暇が与えられるにとどまる。
(5)ア 旧一般職及び地域基幹職は,郵便外務事務,郵便内務事務等に幅広く従事すること,昇任や昇格により役割や職責が大きく変動することが想定されている。他方,新一般職は,郵便外務事務,郵便内務事務等の標準的な業務に従事することが予定されており,昇任や昇格は予定されていない。
また,正社員の人事評価においては,業務の実績そのものに加え,部下の育成指導状況,組織全体に対する貢献等の項目によって業績が評価されるほか,自己研さん,状況把握,論理的思考,チャレンジ志向等の項目によって正社員に求められる役割を発揮した行動が評価される。
イ これに対し,時給制契約社員は,郵便外務事務又は郵便内務事務のうち,特定の業務のみに従事し,上記各事務について幅広く従事することは想定されておらず,昇任や昇格は予定されていない。
また,時給制契約社員の人事評価においては,上司の指示や職場内のルールの遵守等の基本的事項に関する評価が行われるほか,担当する職務の広さとその習熟度についての評価が行われる一方,正社員とは異なり,組織全体に対する貢献によって業績が評価されること等はない。
(6) 旧一般職を含む正社員には配転が予定されている。ただし,新一般職は,転居を伴わない範囲において人事異動が命ぜられる可能性があるにとどまる。
これに対し,時給制契約社員は,職場及び職務内容を限定して採用されており,正社員のような人事異動は行われず,郵便局を移る場合には,個別の同意に基づき,従前の郵便局における雇用契約を終了させた上で,新たに別の郵便局における勤務に関して雇用契約を締結し直している。
(7) 時給制契約社員に対しては,正社員に登用される制度が設けられており,人事評価や勤続年数等に関する応募要件を満たす応募者について,適性試験や面接等により選考される。
第2 令和元年(受)第777号上告代理人樋󠄀 口隆明ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
1 原審は,郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で,同業務を担当する時給制契約社員である第1審原告らに対してこれを支給しないという労働条件の相違及び私傷病による病気休暇として,上記正社員に対しては有給休暇を与えるものとする一方で,上記時給制契約社員である第1審原告 X2に対しては無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違について,いずれも労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると判断した。所論は,原審のこの判断には同条の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。
2(1) 年末年始勤務手当について
第1審被告における年末年始勤務手当は,郵便の業務を担当する正社員の給与を構成する特殊勤務手当の一つであり,12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであることからすると,同業務についての最繁忙期であり,多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において,同業務に従事したことに対し,その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有するものであるといえる。また,年末年始勤務手当は,正社員が従事した業務の内容やその難度等に関わらず,所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり,その支給金額も,実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。
上記のような年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば,これを支給することとした趣旨は,郵便の業務を担当する時給制契約社員にも妥当するものである。そうすると,前記第1の2(5)~(7)のとおり,郵便の業務を担当する正社員と上記時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務手当を支給する一方で,同業務を担当する時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
(2) 病気休暇について
ア 有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては,両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく,当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当であるところ,賃金以外の労働条件の相違についても,同様に,個々の労働条件が定められた趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である(最高裁平成30年(受)第1519号令和2年10月15日第一小法廷判決・公刊物未登載)。
イ 第1審被告において,私傷病により勤務することができなくなった郵便の業務を担当する正社員に対して有給の病気休暇が与えられているのは,上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから,その生活保障を図り,私傷病の療養に専念させることを通じて,その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。このように,継続的な勤務が見込まれる労働者に私傷病による有給の病気休暇を与えるものとすることは,使用者の経営判断として尊重し得るものと解される。もっとも,上記目的に照らせば,郵便の業務を担当する時給制契約社員についても,相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば,私傷病による有給の病気休暇を与えることとした趣旨は妥当するというべきである。そして,第1審被告においては,上記時給制契約社員は,契約期間が6か月以内とされており,第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど,相応に継続的な勤務が見込まれているといえる。そうすると,前記第1の2(5)~(7)のとおり,上記正社員と上記時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,私傷病による病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく,これを有給とするか無給とするかにつき労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,私傷病による病気休暇として,郵便の業務を担当する正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で,同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
3 以上によれば,所論の点に関する原審の判断は,いずれも正当として是認することができる。論旨はいずれも採用することができない。なお,その余の上告受理申立て理由は,上告受理の決定において排除された。
第3 令和元年(受)第778号上告代理人宮里邦雄ほかの上告受理申立て理由第2の2~6について
1 原審は,前記第1の2の事実関係等の下において,郵便の業務を担当する正社員に対しては夏期冬期休暇を与える一方で,同業務を担当する時給制契約社員に対してはこれを与えないという労働条件の相違は労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たり,第1審被告が上記相違を設けていたことにつき過失があるとした上で,要旨次のとおり判断し,第1審原告らの夏期冬期休暇に係る損害賠償請求を棄却した。
第1審原告らが無給の休暇を取得したこと,夏期冬期休暇が与えられていればこれを取得し賃金が支給されたであろうこととの事実の主張立証はない。したがって,第1審原告らに夏期冬期休暇を与えられないことによる損害が生じたとはいえない。
2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
第1審被告における夏期冬期休暇は,有給休暇として所定の期間内に所定の日数を取得することができるものであるところ,郵便の業務を担当する時給制契約社員である第1審原告らは,夏期冬期休暇を与えられなかったことにより,当該所定の日数につき,本来する必要のなかった勤務をせざるを得なかったものといえるから,上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたものということができる。当該時給制契約社員が無給の休暇を取得したか否かなどは,上記損害の有無の判断を左右するものではない。
したがって,郵便の業務を担当する時給制契約社員である第1審原告らについて,無給の休暇を取得したなどの事実の主張立証がないとして,夏期冬期休暇を与えられないことによる損害が生じたとはいえないとした原審の判断には,不法行為に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
3 以上によれば,原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち第1審原告らの夏期冬期休暇に係る損害賠償請求に関する部分は破棄を免れない。なお,その余の上告受理申立て理由は,上告受理の決定において排除された。
第4 結論
以上のとおりであるから,原判決中,第1審原告らの夏期冬期休暇に係る損害賠償請求に関する部分を破棄し,損害額について更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すとともに,第1審被告の上告及び第1審原告らのその余の上告を棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山口 厚 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 深山卓也)
夏期休暇及び冬期休暇
無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例です。
夏期休暇及び冬期休暇について考察します。
その性質・目的は
|
・年次有給休暇や病気休暇等とは別に,労働から離れる機会を与えることにより,心身の回復を図るという目的 |
としています。
そして
| ・職務の内容→相違がある(人事評価においては,担当業務についての評価がされるのみ) ・変更の範囲→相違がある(時給制契約社員は,担当業務に継続して従事し,郵便局を異にする人事異動は行われず,昇任や昇格も予定されていない) ・その他の事情→ |
という事情があると評価しています。
その上で、
| 郵便の業務を担当する正社員と同業務を担当する時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に夏期冬期休暇に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができる |
と判断しています。
つまり、夏期休暇及び冬期休暇の趣旨は、「労働から離れて心身の回復」であり、「職務の内容等につき相応の相違がある」としても、短期間の勤務ではなく,業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている(疲労がたまり休息を必要とする)契約社員に休暇がないのは不合理、という判断です。
1 本件は,上告人と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務した時給制契約社員である被上告人が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と被上告人との間で,夏期休暇及び冬期休暇(以下「夏期冬期休暇」という。)等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して,上告人に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をする事案で
ある。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人は,国及び日本郵政公社が行っていた郵便事業を承継した郵便局株式会社及び郵便事業株式会社の合併により,平成24年10月1日に成立した株式会社であり,郵便局を設置して,郵便の業務,銀行窓口業務,保険窓口業務等を営んでいる。
被上告人は,平成22年6月7日,郵便事業株式会社との間で有期労働契約を締結し,同社及び上告人との間でその更新を繰り返して,郵便外務事務(配達等の事務)に従事する時給制契約社員であったが,同25年12月14日,上告人を退職した。
(2) 上告人に雇用される従業員には,無期労働契約を締結する正社員と有期労働契約を締結する期間雇用社員が存在し,それぞれに適用される就業規則及び給与規程は異なる。
正社員に適用される就業規則において,正社員の勤務時間は,1日について原則8時間,4週間について1週平均40時間とされている。正社員の中には,被上告人と同様の業務に従事する者があるが,正社員は,業務上の必要性により配置転換や職種転換を命じられることがあり,多様な業務に従事している。また,正社員のうちの一定程度の割合の者が課長代理,課長等の役職者となるところ,正社員の人事評価においては,評価項目が多岐にわたり,組織全体への貢献を考慮した項目についても評価されるものとされている。
期間雇用社員に適用される就業規則において,期間雇用社員は,スペシャリスト契約社員,エキスパート契約社員,月給制契約社員,時給制契約社員及びアルバイトに区分されており,それぞれ契約期間の長さや賃金の支払方法が異なる。このうち時給制契約社員は,郵便局等での一般的業務に従事し,時給制で給与が支給されるものとして採用された者であって,契約期間は6か月以内で,契約を更新することができ,正規の勤務時間は,1日について8時間以内,4週間について1週平均40時間以内とされている。そして,時給制契約社員は,担当業務に継続して従事し,郵便局を異にする人事異動は行われず,昇任や昇格も予定されていない。また,時給制契約社員の人事評価においては,担当業務についての評価がされるのみである。
(3) 正社員に適用される就業規則では,郵便の業務を担当する正社員に夏期冬期休暇が与えられることとされている。夏期休暇は6月1日から9月30日まで,冬期休暇は10月1日から翌年3月31日までの各期間において,それぞれ3日まで与えられる有給休暇である。
これに対し,郵便の業務を担当する時給制契約社員には夏期冬期休暇が与えられない。
3 原審は,郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で,同業務を担当する時給制契約社員に対してこれを与えないという労働条件の相違は労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たり,上記相違によって夏期冬期休暇の日数分の賃金に相当する額の損害が発生したと判断した。所論は,原審のこの判断には法令の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。
4(1) 有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては,両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく,当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である(最高裁平成29年(受)第442号同30年6月1日第二小法廷判決・民集72巻2号202頁)ところ,賃金以外の労働条件の相違についても,同様に,個々の労働条件の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である。
上告人において,郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇が与えられているのは,年次有給休暇や病気休暇等とは別に,労働から離れる機会を与えることにより,心身の回復を図るという目的によるものであると解され,夏期冬期休暇の取得の可否や取得し得る日数は上記正社員の勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていない。そして,郵便の業務を担当する時給制契約社員は,契約期間が6か月以内とされるなど,繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく,業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれているのであって,夏期冬期休暇を与える趣旨は,上記時給制契約社員にも妥当するというべきである。
そうすると,前記2(2)のとおり,郵便の業務を担当する正社員と同業務を担当する時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても,両者の間に夏期冬期休暇に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。
したがって,郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で,郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
(2) また,上告人における夏期冬期休暇は,有給休暇として所定の期間内に所定の日数を取得することができるものであるところ,郵便の業務を担当する時給制契約社員である被上告人は,夏期冬期休暇を与えられなかったことにより,当該所定の日数につき,本来する必要のなかった勤務をせざるを得なかったものといえるから,上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたものということができる。
5 以上と同旨の原審の判断は,いずれも正当として是認することができる。論旨は採用することができない。また,その余の上告受理申立て理由は,上告受理の決定において排除された。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
( 裁判長裁判官 山口厚 裁判官 池上政幸 裁判官 小池裕 裁判官 木澤克之 裁判官 深山卓也)
まとめ
日本郵便訴訟では、
・年末年始勤務手当
・病気休暇
・夏期・冬期休暇
・祝日給
・扶養手当 に係る相違について「不合理な格差」という判断を示した。
「職務内容等に違いがある」としながらも、それぞれ「待遇の趣旨を個別に考慮」の上、不合理とされている。
【待遇の趣旨】
・年末年始勤務手当→年末年始に勤務したことへの対価
・祝日給→年始に勤務したことへの対価
→同じ時期に勤務した契約社員に支給がないのは不合理
・夏期・冬期休暇→疲れをとる目的
・扶養手当→家族を持つ者への生活支援を通じ長く働いてもらう目的
・病気休暇→治療に専念してもらい長く働いてもらう目的
→ある程度長く働く見込みの契約社員に支給がないのは不合理
という判断になった。
一方、メトロ・大阪医科大訴訟では
・退職金・賞与→正社員を定着させる目的
→正社員と職務内容等に一定の相違がある契約社員に支給がないのは不合理とまではいえない
という判断。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24