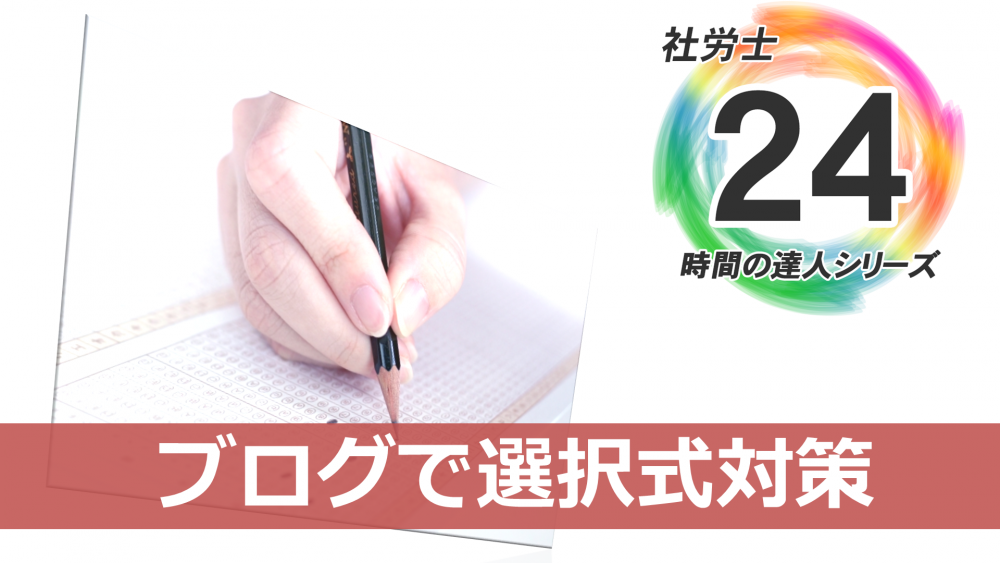皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
賃金支払額の端数処理(正解率70%)
問題
1か月の賃金支払額における端数処理。
”1か月の賃金支払額に生じた【?】円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと”は労働基準法第24条の賃金支払いの原則に違反しない。
A 1
B 100
C 1,000
D 10,000
社労士試験に合格するためのシンプルな学習スケジュール
社労士試験の学習スケジュール・学習計画の作り方。講師歴23年でヒアリングした合格者のスケジュールを一般化。独学の方にもおすすめです。ブログ版→https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/13347担当:金沢博憲(#社労士24、経験者合格コース)【INDEX】0:00→スケジュー...
解答・解説
「C 1,000」。
1か月の賃金支払額に1,000円未満の端数が生じた場合は、次の月に繰り越すことが可能。
例えば、その月の賃金が300,800円であったら、800円を翌月に繰り越し、その月は300,000円を支払えばよい。小銭での支払がなくなるメリットがある。
【端数処理が適法となる場合】
・1か月(1日×)の時間外労働等の時間数の合計→1時間未満を四捨五入
・1時間当たりの賃金額→1円未満を四捨五入
・割増賃金額→1円未満を四捨五入
・1か月の賃金支払額→100円未満を四捨五入
・1か月の賃金支払額→1,000円未満を翌月繰越払い
関連論点
- いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
- 労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労使協定(労働協約ではない)に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。
- 賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。
- 使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。
- 「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはない。
- 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている場合において、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じたときは、過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する規定(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。
- 労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない(少額でありさえすれば、相殺が認められるわけではない)」とするのが、最高裁判所の判例である。
- 1か月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
- 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
- 最高裁の判例によると、労働基準法第24条第1項ただし書の要件を具備する「チェック・オフ(労働組合費の控除)」協定の締結は、これにより、同協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法第120条第1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎない、とされている。
- 「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(以下「中間利益」という。)を得たときは、使用者は、当該労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができる(「使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されない」わけではない)が、上記賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である(あけぼのタクシー事件)。
- 賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は有効である(大和銀行事件(昭和57年10月7日))。
- ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の判例である(三菱重工業長崎造船所事件(昭和56年9月18日))。
- 労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえず、したがって、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負わないとするのが最高裁判所の判例である(水道機工事件(昭和60年3月7日))。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
電通事件(平成12年3月24日)
長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた労働者がうつ病にり患し自殺した場合に使用者の損害賠償責任が肯定された事例
「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。」
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
不安を感じるのは自然なこと。
真剣であるほど。合格が近づくほど。
そんな不安と向き合いながら、前に進む方が、合格の扉を開く。
自分を前に進めるための仕掛けが、計画。
「これをやる」と決めて機械的に進めていく。
自分への予告状。
追いかけるのも自分。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。