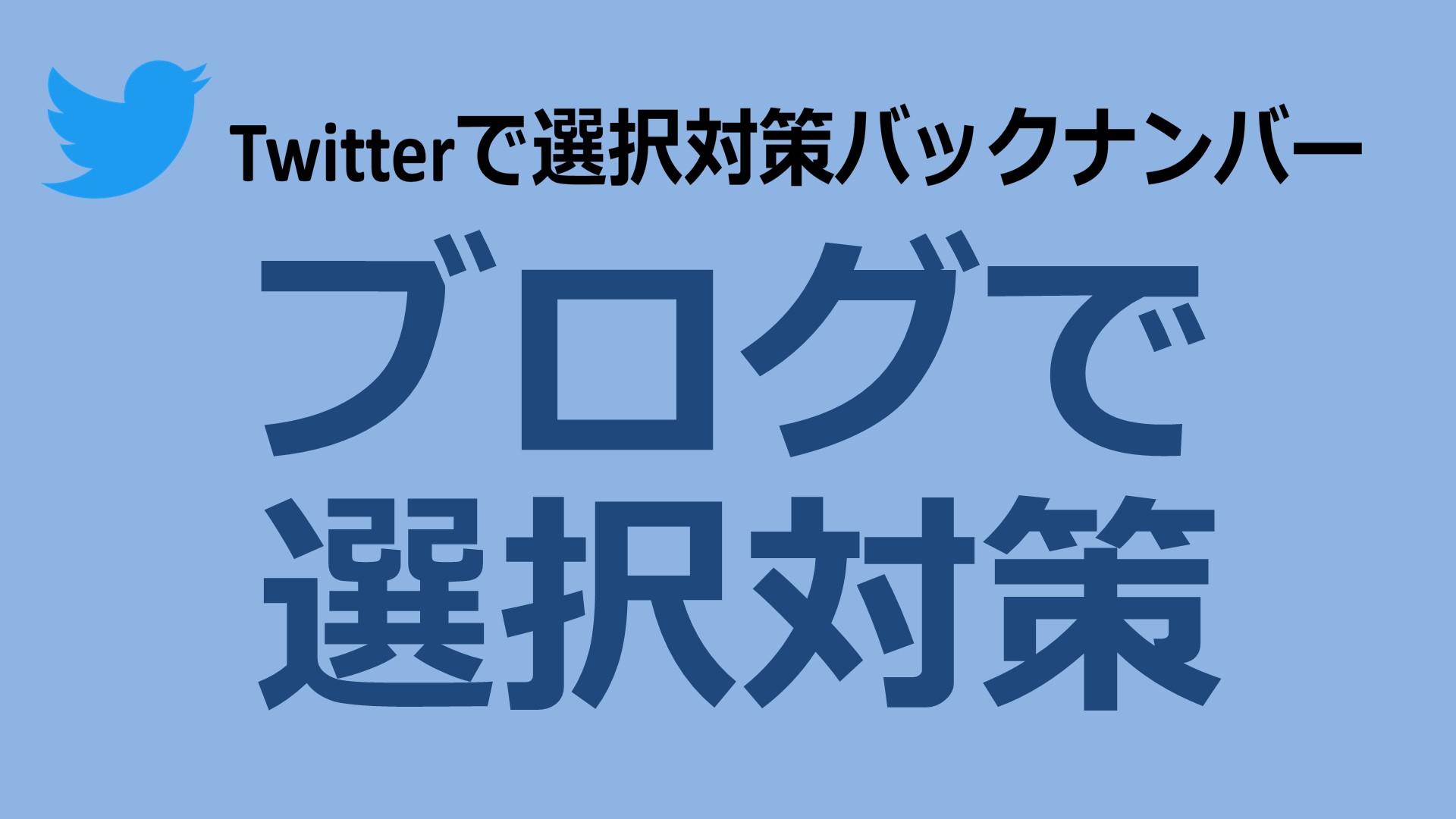皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
部分算定日における休業補償給付の額(正解率60%)
問題
・労働者が一部労働不能の日
・給付基礎日額:12,000円
・労働に対して支払われた賃金の額:5,000円
・年齢階層別最高限度額:10,000円
上記の場合の休業補償給付の額は?
A 1,000円
B 2,200円
C 3,000円
D 4,200円
科目別難易度・攻略法【ブログ】
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 この記事では、社労士試験の科目別攻略法をご紹介します。 社労士試験の科目数は10科目 社労士試験の試験科目は10科目です。 「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災 …
解答・解説
「D 4,200円」。
①一部労働不能の場合の計算式を想起
・(給付基礎日額ー賃金)※×60%
※最高限度額は”賃金控除後”に適用
②数値当てはめ
・(12,000円-5,000円)※×60%=4,200円
※7,000円<10,000円→最高限度額の適用なし
この取扱、本試験でよく出題されますが、一言で片付く魔法の言葉があります。初手は賃金を引く、です。
すなわち、賃金を引いた後に最高限度額を適用する、60%をかけるということです。
少し昔の解説動画。
関連論点- 療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
- 業務上の事由による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付は、支給されない。
- 業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。
- 「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。
- 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされる(雪島鉄工所事件)。
- 休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付は支給されない。
- 業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
- 業務上の事由による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。
- 休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。
- 休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。
- 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
- 傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。
- 休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日につき、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入される。
- 業務上の傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。
- 労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額×)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である(最高限度額は給付基礎日額に適用せずに、「給付基礎日額-賃金」の額に適用する)。
- 労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、賃金と休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の84%(100×)となる。
【例】給付基礎日額1万円、賃金2千円
・休業補償給付→(1万円-2千円)×60%=4,800円
・休業特別支給金→(1万円-2千円)×20%=1,600円
・賃金+休業補償給付+休業特別支給金=8,400円
- 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合にも、休業補償給付の額が減額調整される。
- 休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる(参考サイト)。
- 労働者が、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
- 休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。
- 複数事業労働者については、複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要がある。例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となる。ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、労災法第14条第1項本文の「労働することができない」に該当すると認められることがある。
- 休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。(通達)
- 複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行う。その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱う。一方、全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は労災法第14条第1項の「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
細谷服装事件(昭和35年3月11日)
昭和24年8月に、会社が従業員を解雇予告なしで解雇の通知をした(その後、昭和26年3月に昭和24年8月分の給料と解雇予告手当の支払い)。従業員は、昭和26年3月までの未払賃金と、解雇予告手当と同額の付加金を請求をした。最高裁は、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し会社の義務違反の状況が消滅しており、付加金請求をすることができないとした。
「付加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものであるから、使用者に労働基準法第20条の違反があっても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は、附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
社労士試験合格に必要な ”がむしゃら” さ。
がいよう(概要)から入る
むだ、ムラをなくす
しゃかい保険科目で稼ぐ
らいばるは昨日の自分
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。