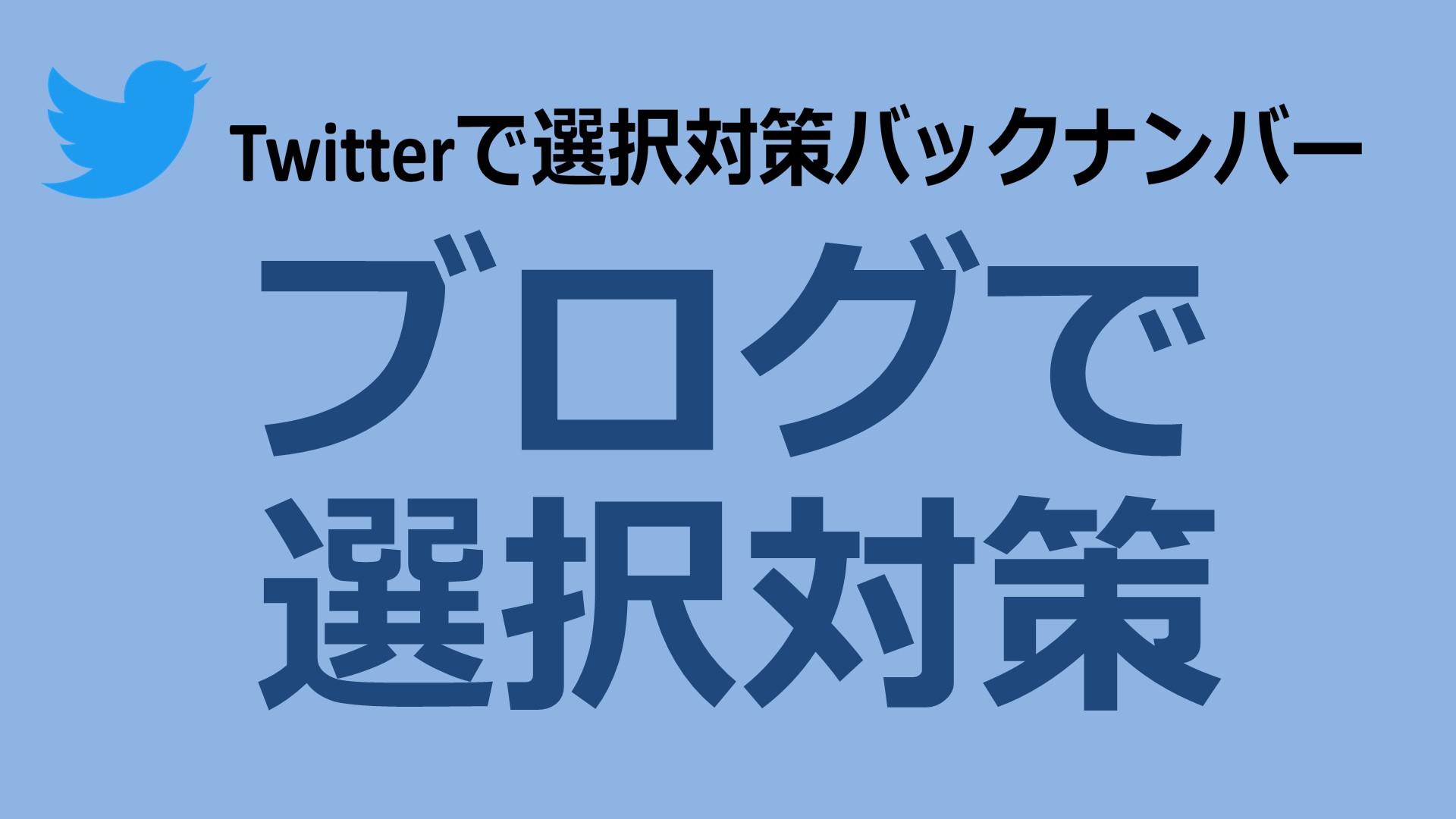皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
全労働日(正解率50%)
問題
労働者Aの令和7年4月1日~令和8年3月31日の状況。
・就業規則上の所定休日:125日
・年次有給休暇取得日:5日
・正当な争議行為による休業日:10日
令和8年4月1日に付与する年次有給休暇の出勤率の算定にあたって、直近1年間の全労働日は【?】となる。
A 225日
B 230日
C 240日
D 365日
合格体験記は勉強方法という名の宝の山。
100人の合格者には100通りの勉強方法がある。
ご自身にあった勉強方法を探してみましょう。
過去にお寄せ頂いた合格体験記です。 2024年対策
解答・解説
「B 230日」。
①全労働日は、所定休日を除いた日数
②全労働日から次の休業日は除外される
・不可抗力
・使用者側に起因する経営障害
・正当な争議行為など
①365日ー125日(所定休日)=240日
②240日-10日(争議)=230日
なお、年休取得日は、全労働日・出勤日に算入。
関連論点
- 労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることにある。
- 労働者派遣法の規定によるいわゆる紹介予定派遣により派遣されていた派遣労働者が、引き続いて当該派遣先に雇用された場合には、年次有給休暇の規定の適用については、当該派遣期間については、年次有給休暇付与の要件である継続勤務したものとして取り扱う義務はない。
- 年次有給休暇の権利は、雇入れの日から3か月しか経たない労働者に対しては発生しない(雇入れから6か月間の継続勤務が必要なため)。
- 年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しなければならない。
- 年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれる。
- 年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定においては、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間のほか、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、出勤したものとみなされる(生理日休業や子の看護休暇を取得した期間は出勤したものとはみなされない)。
- 6週間以内に出産する予定の女子が、労働基準法第65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、産前休業の期間が、結果的には産前6週間を超えた場合に、当該超えた部分の休業期間は、出勤したものとみなす必要がある。
- 年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
- 年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」における全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。したがって、所定の休日に労働させたとしてもその日は全労働日に含まれない。
- 不可抗力による休業日、使用者側に起因する経営障害による休業日及び正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日については、ここでいう全労働日に含まれない。
全体像から個別の規定に落とし込む講義。担当講師:金沢博憲(#社労士24、経験者合格コース)経験者合格コースの詳細https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_detail?id=12738
以上、今回の問題でした。
毎日判例
「「労働者の過半数を代表する者」であったか否かについて検討するに、「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により適法に選出されなければならないが、適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要というべきである。」
「親睦団体の代表者が、自動的に「過半数代表者」として36協定を締結したにすぎないときには、協定当事者が労働者の過半数を代表する者ではないから、36協定が有効であるとは認められない。」
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「択一の点を挙げるにはどうすればいいでしょうか?」
「残像だ」
「はい?」
テキストを”ビジュアル”として捉えて、問題を解くときに「あの辺の右側にのっていたところだ」「あの表でまとまっていたところだ」という”テキストの残像”を足がかりに解答する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。