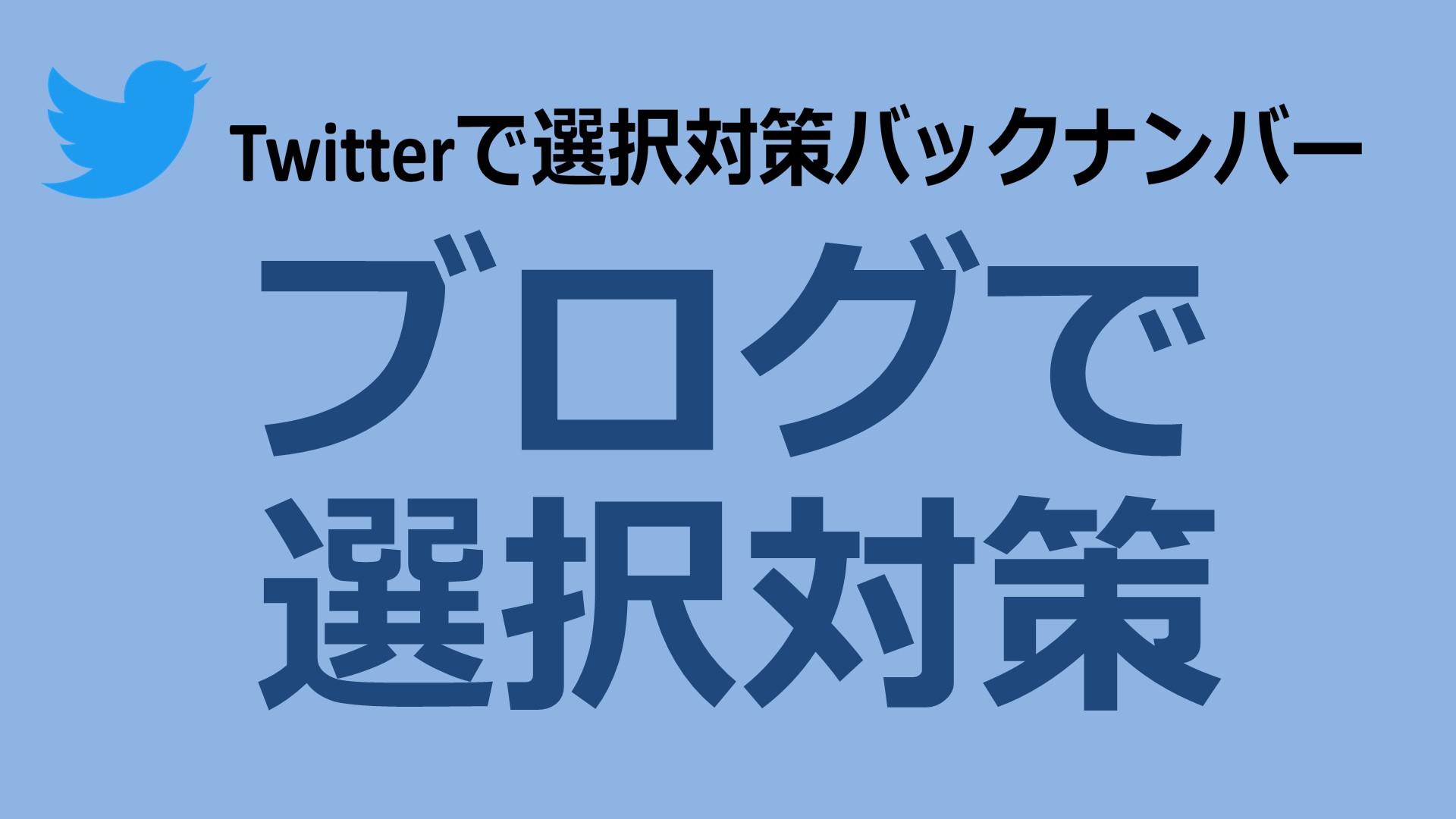皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
年次有給休暇の付与日数(正解率56%)
問題
雇入れからの継続勤務期間が1年6か月を経過した日において、「1日の所定労働時間が8時間かつ週所定労働日数が4日」である労働者について発生する年次有給休暇の日数は?
※過去1年の出勤率は80%以上
A 9日
B 10日
C 11日
D 12日
試験の解き方、11のキホン
社会保険労務士受験生の皆様こんにちは。 本日はいわゆる科目ごとの最後に実施される確認テスト(大原でいう定例試験)の解き方、基本のきをご紹介します。 直前期の模擬試験、そして本試験本番にも通じるポイントです。 (1)親問題 …
解答・解説
「C 11日」。
論点が2つ。
・論点①→通常付与と比例付与の判別
「1日の所定労働時間が8時間×週所定労働日数が4日」→週所定労働時間が30時間以上のため、通常付与。
・論点②→継続勤務年数に応じた加算日数
「1年6か月継続勤務」→10日に1日加算され11日。
- 令和3年4月1日に雇い入れられた労働者であって、週所定労働日数が5日であるものが、令和4年10月1日から1年間休職し、令和5年10月1日から勤務を再開して令和6年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は、同年10月1日以降、当該労働者に、14労働日の年次有給休暇を与えなければならない。(週所定労働日数が5日であるため通常付与の対象であり、継続勤務期間が3年6か月であるため、付与日数は14労働日になる。)
- 使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、両者とも通常付与の対象となるため、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
- 月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、10労働日である。
- 月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、10労働日である。
- 労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、休暇は基準日において発生するので、当該6か月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
- 1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、休暇は基準日において発生するので、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
- 年次有給休暇は、暦日単位で付与しなければならないが、労使協定に定めをすることにより、時間単位で付与することが認められている。
- 年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、年5日(10日×)の範囲内で認められている。
- 労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することはできない。
- 労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。
- 所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間(2.5時間を切り上げて3時間)に変更される。(年の途中で所定労働時間数の変更があった場合には、時間単位の端数が残っている部分は、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることになるため。)
- 年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。
- 労使協定により年次有給休暇の計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。
- いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれるところから、前年度から年次有給休暇日数が3日繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者については、繰り越し分を含めた15日分の権利のうち5日を超える部分である10日に限り計画的付与の対象とすることができる。
- 年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、事業場全体で一斉に付与することができ、また、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることもできる。
- 労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。
- その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
- 使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
- 令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年3月31日(令和7年9月30日ではない)までに時季を定めることにより与えなければならない(法定の基準日より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合には、使用者は、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければならないため)。
- 使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、労働基準法第39条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、労働基準法第39条第8項の「日数」には含まれないとされている。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
関西医科大学研修医(未払賃金)事件(平成17年6月3日)
臨床研修として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事する医師は,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、労働基準法の労働者に当たるとされた事例。
「この臨床研修は,医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり,教育的な側面を有しているが,そのプログラムに従い,臨床研修指導医の指導の下に,研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして,研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には,これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り,上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。
これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件病院の耳鼻咽喉科における臨床研修のプログラムは,研修医が医療行為等に従事することを予定しており,乙は,本件病院の休診日等を除き,上告人が定めた時間及び場所において,指導医の指示に従って,上告人が本件病院の患者に対して提供する医療行為等に従事していたというのであり,これに加えて,上告人は,乙に対して奨学金等として金員を支払い,これらの金員につき給与等に当たるものとして源泉徴収まで行っていたというのである。
そうすると,乙は,上告人の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして労働基準法9条所定の労働者に当たり,最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべきであるから,上告人は,同法5条2項により,乙に対し,最低賃金と同額の賃金を支払うべき義務を負っていたものというべきである。」
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「100個の知識×100%の精度」で憶えるのが理想。
しかしそれは難しい。
であれば「100個×70%」ではなく「70個×100%」を目指す。
失点問題は
①「なんでコレを間違えたかな」問と
②「こんなの知らない」問
の2種類。
①が圧倒的に多い。
前者を潰せば合格ラインにのる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。