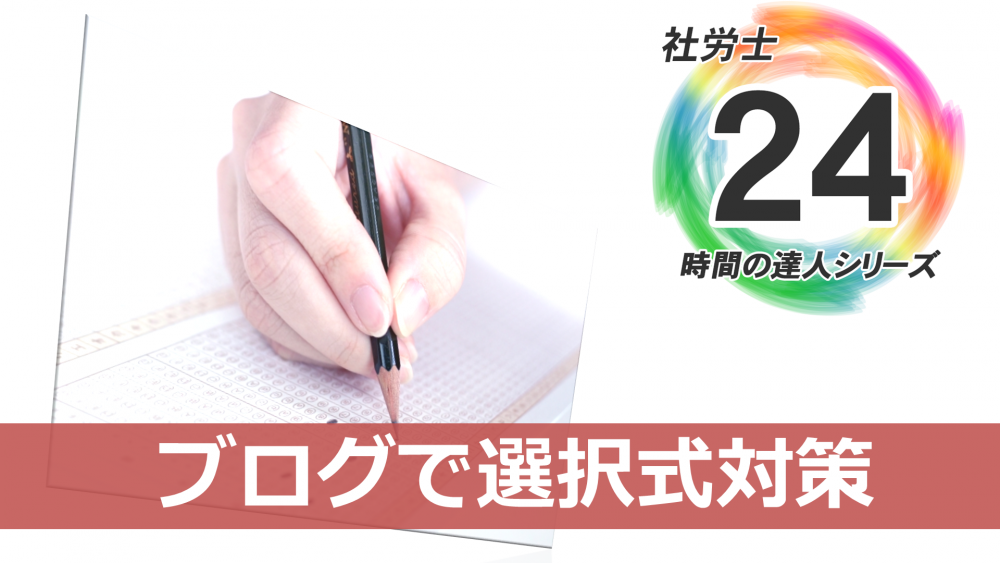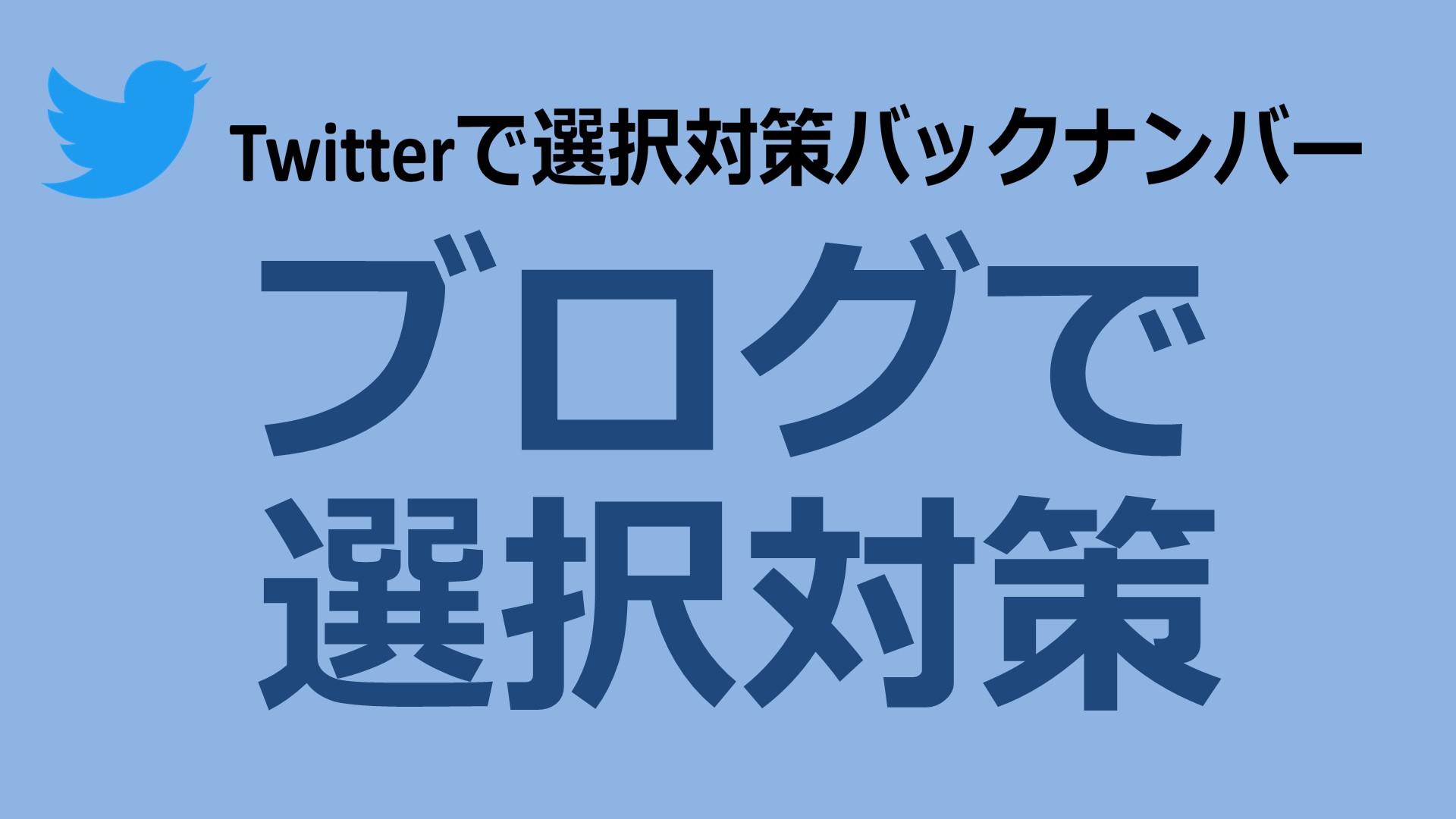皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
「強制労働の禁止」違反の罰則(正解率74%)
問題
「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
対応する罰則は「【?】の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」。
A 1年以下
B 1年以上10年以下
C 3年以下
D 3年以上10年以下
【罰則】との向き合い方はこちら。
ただの罰則の過去問まとめです。 平成11年以降。 罰則規定はどの程度押さえる? ・択一→出題回数が多い労基・安衛で、平成11年~令和元年にかけて23肢。1科目につき1年で1肢、出るかどうか。 ・論点は「罰則があるかないか …
解答・解説
「B 1年以上10年以下」。
なお、刑法改正により、懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑を創設(令和7年6月1日施行)している。
関連論点- 労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。
- 労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
- 労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
- 労働基準法第5条に定める「監禁」とは、一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、必ずしも物質的障害を以って手段とする必要はない。(「物質的障害がない場合には監禁に該当しない」わけではない)
- 使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。
- 労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則が定められている。
- 強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。※法条競合とは、一つの行為が複数の刑罰法規に該当していても、そのうちの一つだけが適用され、他は排斥される関係をいう。すなわち、5条違反の罪のみが成立して、刑法の暴行罪等は成立する余地がない。
- ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、当該賃金不払いについては、当該代表者及び法人企業(法人企業に対してのみではない)に対して罰則が科される。
- 労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。
- ある法人企業の代表者が、当該企業において、労働基準法第37条の規定に違反する時間外・休日労働(いわゆる不払い残業等)が行われている事実を知り、その是正に必要な措置を講じなかったときは、たとえ代表者自らが当該不払い残業等を指示、命令していなくとも、当該代表者も行為者として処罰される。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
朝日放送事件(平成7年2月28日)
雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法七条にいう「使用者」に当たるとされた事例
「事業主が雇用主との間の請負契約により派遣を受けている労働者をその業務に従事させている場合において、労働者が従事すべき業務の全般につき、作業日時、作業時間、作業場所、作業内容等その細部に至るまで事業主が自ら決定し、労働者が事業主の作業秩序に組み込まれて事業主の従業員と共に作業に従事し、その作業の進行がすべて事業主の指揮監督の下に置かれているなど判示の事実関係の下においては、事業主は、労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあり、その限りにおいて、労働組合法七条にいう「使用者」に当たる。」
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「まとまった時間があるとかえって勉強がすすまない」打開策
・やることを事前決めておく。「何しようかな~」の時間がもったいない
・25分の勉強+5分の休憩(ポモドーロ・テクニック)。3時間なら、30分×6セット。締切効果でタスク遂行
・科目、場所、やることを変える。飽きを防ぐ
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。