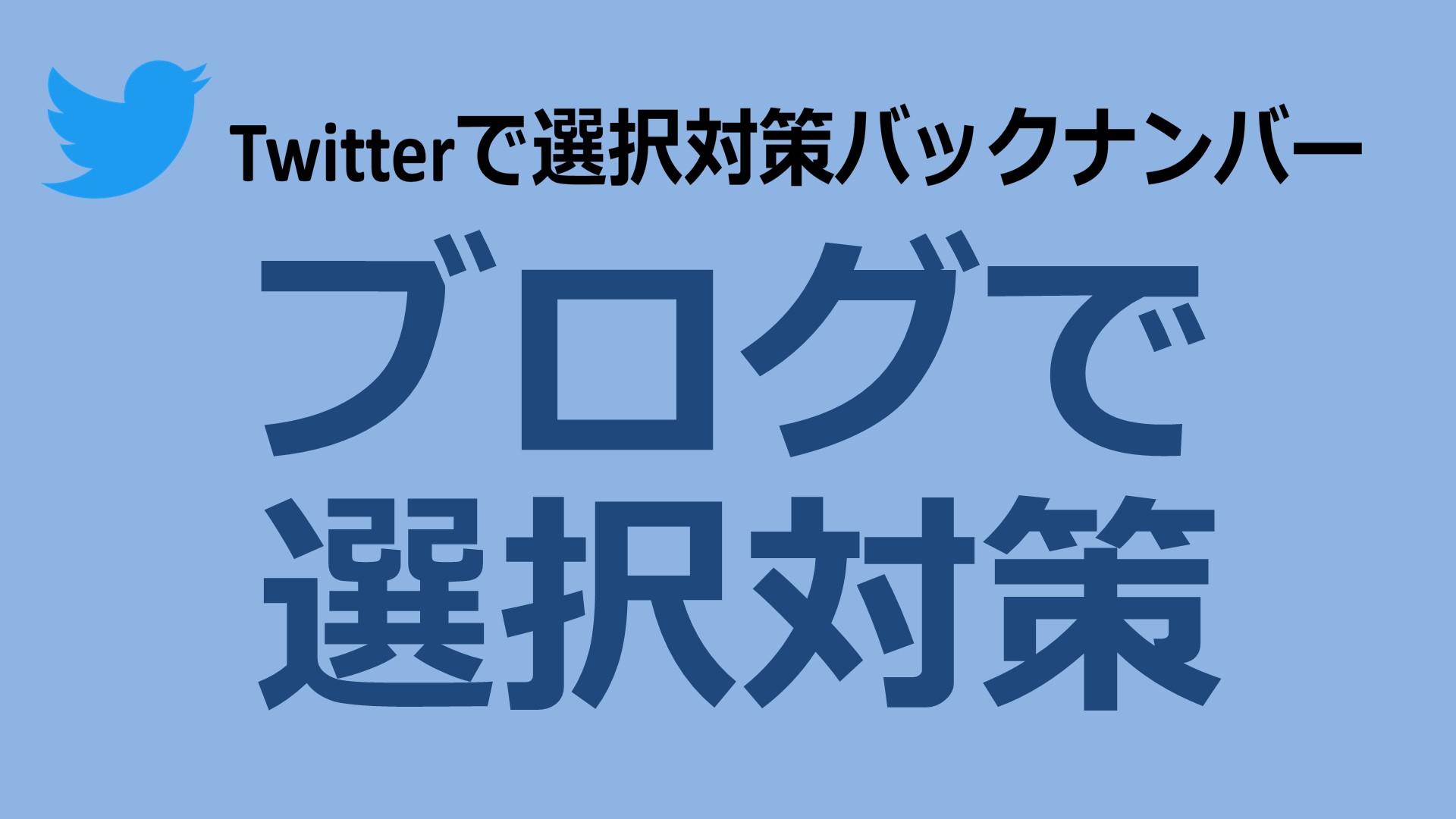皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
一斉休憩(正解率43%)
問題
休憩時間は、【?】の事業については、原則として一斉に与えなければならないとされているが、労使協定を締結した場合、一斉に与える義務はない。
A 金融
B 接客
C 倉庫における貨物の取扱い
D 電気通信
【令和7年試験社労士試験】高得点者の点の取り方(択一解説)
「取るべき問題で取れなかったのはどの問題か」「なぜ取れなかったのか」「どうすれば取れるようになるのか」を検証する必要がある。
そのための最高の教材は、ご自身が解いた今年の本試験問題。
ぜひ振り返りをして欲しい。
高得点者はどの問題をとって、どの問題を取れなかったか。どのような思考回路で解いたのか。択一式試験の問題を実況中継風に解説します。#社労士240:00 はじめに1:28 問1 絶対とりたい!4:44 問2 とれたらすごい!7:46 問3 絶対とりたい!9:08 問4 絶対とりたい!12:30 問5 絶対とりたい!
解答・解説
「C 倉庫における貨物の取扱い」。
一斉休憩の適用除外業種
〇 運輸交通業 〇 郵便通信業 〇 商 業
〇 保健衛生業 〇 金融広告業 〇 接客娯楽業
〇 映画・演劇業 〇 官公署
※「倉庫における貨物の取扱い」はない。
上記の業種は、運送業務や顧客・利用者対応の業務(運ぶ、繋ぐ、接客する)など、一斉に休憩させると業務が成り立たなくなる性質があるため、労使協定の締結がなくても交替休憩を実施できる。
また、上記以外の業種でも、労使協定を締結した場合(届出は不要)、一斉に与える義務はない。(例外の要件は労基署長の許可ではない。)
基本論点だが正解率43%。
交替制には2種類ある
①労使協定が無くても交替制が可能な業種
②労使協定があれば交替制が可能な業種
↓
本問は②の業種に該当する
↓
①の業種を想起する
↓
①の業種に含まれないのは「倉庫における貨物」のみ
どの過程で間違えたか分析するのが大事。
関連論点- 労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
- 工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
- 「使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされているので、1日の労働時間が16時間を超える場合でも少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えれば足りる。
- 使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、労働時間が6時間以下であるため、休憩時間を与えなくてよい。
- 本条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。
- 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは(「労働基準監督署長の許可を受ければ」ではない)、使用者は、その定めに基づき、休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
- 休憩時間は、本条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業(「倉庫における貨物の取扱いの事業」は一斉休憩の付与が適用される)には、この規定は適用されない。
- 労働者が事業場内において自由に休息し得る場合には、外出について所属長の許可を受けさせても違法にはならない。
- 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。
- 労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。
- 企業秩序維持の見地から、休憩時間内に職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許される許される。
- 休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約である。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
「労働基準法二四条一項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法一二〇条一号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである。」
「したがって、使用者と労働組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であって、右委任が存しないときには、使用者は当該組合員の賃金からチェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である。そうすると、チェック・オフ開始後においても、組合員は使用者に対し、いつでもチェック・オフの中止を申し入れることができ、右中止の申入れがされたときには、使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止すべきものである。」
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
受験生あるある「テキストがマーカーだらけ」 にしない方法。
①講義中はマーカーで引かない(鉛筆又はフリクションで引く)
②十分な復習後に本当に大事だと思うキーワードに絞って引く
③色は増やしすぎない。例えば青・赤の二色。原則規定は青、例外規定は赤など。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。