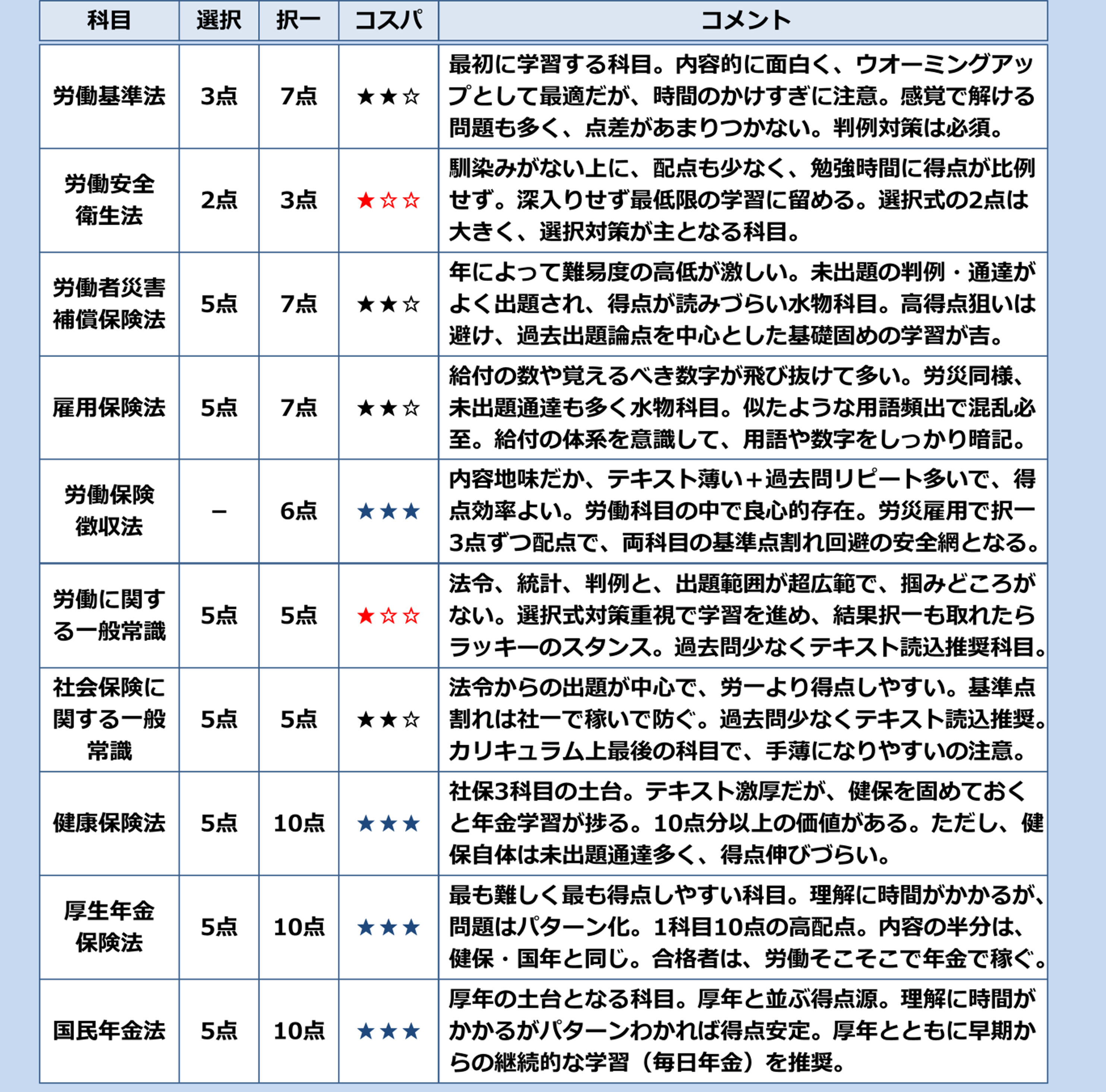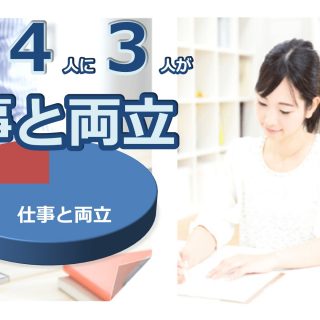皆さんこんにちは。
金沢博憲(社労士24 担当講師)です。
2025年社労士試験に合格された皆様からの合格体験記をご紹介します。
今回は在胡様からお寄せ頂いた体験記です。
誠にありがとうございます。
#社労士24 #経験者合格コース #社労士合格体験記
合格体験記は11月30日までに募集中です。応募フォームは→こちら
プロフィール
40代後半、男性、労働安全衛生コンサルタント事務所を経営しています。
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの資格を所持しており、各種安全衛生に関する法定講習・特別教育・職長教育の講師や、企業の安全衛生診断・改善指導を業として営んでいます
初受験は令和4年で、かれこれ4年かけて合格できました。
【社労士を目指したきっかけ】
労働安全衛生コンサルタント仲間に、社労士と労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントのトリプルライセンス所持の方がおられ、両資格を活用して活躍されているのを見て、触発されました。
お客様と話していると、ハラスメントなどの労務領域の相談をされることがあり、その領域のコンサルティングを行うには社労士の資格が有効だと思いました。
【得点状況】
2022年:択一29点 選択:4科目割れ
2023年:択一38点 選択:2科目割れ
2024年:択一38点 選択:割れなし(労一2点救済)
2025年:択一:(7/7/8/7/4/7/7:47点)
選択:(4/3/5/3/3/4/4/4:30点)
※今年救済を待たずとも合格点に届いていたのは、間違いなく社労士24で基礎をがちがちにしていたおかげだと思います。
【利用のコンテンツ】
2022年:完全独学、市販のテキスト+問題集のみ(実質3か月の勉強のみ)
2023年:2022年と同様
2024年:他社通信教育
2025年:社労士24+直前対策、月間社労士(白書統計の号と模試の号のみ)、他社模試を2回(5月:LEC、6月:クレアール)、他社の市販模試(LEC)※金沢先生のブログは毎日チェックし、問題演習を行っていました。
【学習計画の立て方】
1年目はお試し受験のつもりで、4月から問題集とテキストを次年度のために軽く流した程度でした
2年目から本格的に勉強開始しましたが、まずは独学で行こうと、他社のテキストと基本問題集、過去問題集を中心に演習を行いました。
この年は他の資格試験と並行して勉強をしていたので、本格的な勉強は1月からでした。不完全燃焼の感があり、点数もそこまではのびませんでした。
3年目は、前年度の反省から、独学での合格は難しいと考え、他社の通信教育を受けました。
しかし、教材のボリュームに圧倒されて、テキストと基本問題集をこなすのに手いっぱいで、配布された全範囲(直前演習・模試・判例・白書統計など)を終えることができませんでした(この年は、安衛法の化学物質関係の大きな法改正があったため、雑誌記事・書籍執筆依頼、法定講習の講師依頼、相談依頼が多く、超繁忙年で時間が取れなかったことも理由にあります)。
とはいえ、自分なりにこの年はかなり時間・労力をかけて取り組んだにもかかわらず、択一の点数が前年比で1点も伸びなかったことで、勉強のやり方に根本的な誤りがあると感じました。
次年度は、要点がまとまったもっとコンパクトな教材で基礎中心に勉強したいと思い、労働安全衛生コンサルタント会に所属している労働安全コンサルタント+労働衛生コンサルタント+社会保険労務士のトリプルライセンスの先輩に相談したところ、社労士24を勧められました。
4年目は、社労士24を中心に9月から勉強を勧めました。
まず、「社労士24を2倍速で視聴し、択一トレ問に取り組む。間違った問題は印をつけて、再度間違った問題だけで解きなおし、全問正解できるようになるまで繰り返す」をワンセットとし、これを3セット行う。
そのあと選択式トレ問に取り組んで、次の科目へ移るというのを愚直に繰り返しました。
時間に余裕ができた期間は、前の科目の復習に充てました。
(なお、全年度を通して、労働安全衛生法は特に勉強しなくとも、普段の業務での知識だけで点を落とすことはないと思いましたので、過去問1周した以外に、手は付けていません。)
直前期は、白書統計対策を5月上旬から行い、単語帳を作り、少なくともこれだけは覚えて会場に行くという範囲を自分で決めました。
また、目的条文については、横断対策の該当部分を毎日寝る前に暗唱することを行いました。
5月以降は(他社も含め)、模試を月1回以上受けるようにし、応用力を養うことを意識しました。
模試は他社2回、大原2回の計4回受けています。各々復習、見直しは2回以上行っています。
【勉強時間の作り方】
週の初めに、その週のおおよそのスケジュールを立て、毎日最低1時間は勉強する。
週最低20時間は勉強する、という方針で臨みました。
1月以降は週1回は社労士の勉強だけに集中できるような日を作ることを意識して、スケジュールを組みました。
主に就寝前を勉強時間に充て、それ以外に自動車・電車の移動中には社労士24の動画視聴または単語帳・サブノートの確認を行っていました。
【1日平均の勉強時間とトータルの勉強時間】
少なくとも1日1時間以上は必ず勉強時間を作る。
週に20時間は勉強時間を作ることを意識し、毎週のスケジュールを組みました。
直前期は1日2時間以上、週30時間以上をノルマとしました。
トータルの勉強時間は1300~1500時間くらいだと思います
【回転数】
- 社労士24の講義:画面を見ながらは全科目10周以上、移動中のながら聞きを含めると数知れず※なお、講義はすべて2倍速で見ています
- 択一トレ問:科目によって異なりますが、13~15周くらい
- 選択トレ問:各科目3周、労一、社一のみ5周
- 直前対策の統計問題:5周
- 各種模試、直前対策の各種演習問題:2~3周
【一番苦労したことと解決した方法】
テキスト・問題集の繰り返しだけだとどうしても頭に定着しないもの(雇用の届け出期限、健保の高額医療、徴収の届け出先・届出期限など)がありました。そういったどうしても覚えなければいけない細かい数字などは、100均でB6の小さいノートを買ってきてサブノートにまとめ、それを常に持ち歩いていました。
前年の労一2点の経験から、白書・統計をおろそかにできないと思い、単語帳に重要数値をまとめました。
最直前期は、寝る前に重要事項サブノートを一周、白書・統計単語帳を一周を、自らのノルマに課しました。
【選択式の勉強方法】
選択のトレ問を中心に勉強したのと、模試・直前対策:選択式の復習を行いました。
選択式のトレ問は、各科目の勉強時に1回、7月に1回転、8月に1回転させています(労一と社一だけは、7月+1回、8月+1回解いてます)。
また、7月後半~8月の前半に、月間社労士の模試、LECの市販模試の選択式だけをやり、選択式に対するカンを鍛えました。
【不合格だった年の原因と今回変えたこと】
不合格だった年は、テキストのボリュームが多すぎて、テキストを繰り返し読み込むことができなかったことと、問題演習に十分に時間が取れなかったことが敗因だと思っています。
社労士24のように基本がギュッと詰まったテキストを繰り返し読み返すことと、演習をしつつテキストに追加で情報を書き込んでいくことで、テキスト情報量の密度を上げていったことが、今回の勝因だったと思っています。
【勉強内容】
・5月まで(直前期の前)
基本的には届いた教材の配達スケジュールをベースに、次の教材が来るまでに社労士24を倍速で3周視聴・択一トレ問3周以上、選択トレ問1周以上を各サイクルに行いました。
また、昨年まで使用した教材なども利用しながら、最低月1回は全科目の予習・復習の演習を行いました。
・5月~7月(直前期)
全科目一巡後は、白書・統計対策を加えつつ、社労士24視聴⇒テキスト通読⇒択一トレ問を全科目ひたすら回転させました。
白書統計のテキスト到着後は、統計の問題もサイクルに組み込みました。
直前対策の演習問題については、ただ解くだけでなく、各分冊間違えたところを中心に2回以上復習する時間を作りました。
また、寝る前に「毎日目的条文の暗唱」「隔日判例テキスト通読」「隔日白書テキスト通読」を行いました。
これは後述の模試の結果から、合格を左右するのは労一、社一の選択であるように感じていたので、その対策として実施しました。
そのほかに、毎日単語帳・サブノート見直しを行っています。
7月くらいになると、択一の問題もおおよそ覚えてきたので、テキストの読み込みの割合を上げていきました。
また、5月から毎月1回以上模試を受けることにし、計4回受けています。
今思えば、正直言って模試はこんなに受ける必要はなかったようにも思いますが、5月・6月の模試がそこそこ良い結果(5月択一43点、6月択一47点、各々選択1科目割れあり)であったのは精神安定上では、良かったと思っています。
模試を受けるたびに点数が上がっていき、最後の7月の大原の模試は択一1回目61点、2回目47点、両回とも選択割れなしと、良い結果が出たのでほっとしたのを覚えています。
・8月(最直前期)
「毎日目的条文」「隔日判例」「隔日白書」は続けつつ、第1~2週目は、直前対策・模試の間違えたところを中心に復習をしました。
第3~第4週は、社労士24の全科目一気見、テキスト通読、択一トレ・選択トレの間違えたところを中心に振り返りました。
最後の3日間は完全に勉強だけに充てられるようスケジュールを調整し、社労士24の2倍速での一気見、テキストの読みこみ、サブノート・単語帳の見直し・消しこみを行いました。
試験会場にはサブノートと単語帳を持っていき、移動中・休憩時はそれをひたすら見返していました。
【本試験中に気をつけたこと・感じたこと】
択一の問題を解いていると、あまりの難易度に心が折られそうになりましたが、試験前に金沢先生がアップしてくださった「1年間の頑張りを解答用紙においてくれば必ずいい結果になります」という言葉を信じて、自分を信じて問題を解いていきました。
私の場合、4回受けた模試のすべてを通じて、全回とも択一の5番目に解いた科目が一番悪いという傾向がありました。
解く科目の順番を変えてもこの傾向は変わりませんでしたので、これは体力・集中力が5科目めあたりで切れるという意味だと解釈しました。
そこで本番の試験では一般常識(択一の4科目目)を終えた時点でトイレに行き、深呼吸・ストレッチをしてリラックスをするという作戦をとりました。
今回も5科目目の健保が4点とギリギリでしたが、この時が疲れのピークでした。
トイレでの深呼吸・ストレッチによる疲れリセットをしていなければ、おそらく落ちていたのではないかと思います。※模試は、こういった試験時の体調管理・疲労管理の作戦を練るうえでも重要な位置を占めています。
ご自分の作戦を立てることをお勧めします。
金沢先生も動画でおっしゃっていた通り、「最初の直感で選んだ肢は、根拠がない限り変えない」を徹底しました。
解いた後の見直しで「なんとなくこっちの気がする」という問題もいくつかありましたが、根拠がない限りは変更しないを貫きました。
結果として、全科目選択3点以上、択一4点以上を確保できましたので、この方針は正しかったと思います。
もし悪魔のささやきに負けていたら、選択の労災と社一は2点になっていました(結局2点でも救済があったのですが、それはそれです)。
【受験生の方へのメッセージ】
勉強中、社労士24だけでは足りないのではないか?という思いが生じたときもありましたが、やはり「基礎をゴリゴリに固めるのが最短ルート」なのは間違いないです。
それを行うのに私には社労士24+直前対策パックが最適の教材だったと思います。
私の場合は、サブノートと単語帳を作るという方法で勉強しましたが、皆さん各々に合った勉強方法・ペースを見出すことが、まずは大切だと思います。
そのうえで、社労士24と金沢先生を信じて、基本を確実に押さえる、これを徹底すれば、結果は必ず付いてきます。
頑張ってください。
【その他ご感想など】
この資格は、家族の協力がなければ、合格できることはない資格だと思います。
3年間、毎年夏は遊びにも連れて行ってやれない父を、恨み言一つ言うでもなく、むしろ応援してくれた妻と娘には、心から感謝しています。
その他の合格体験記
その他の合格体験記は下記のリンク先でご覧いただけます。
過去にお寄せ頂いた合格体験記です。 2024年対策
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24