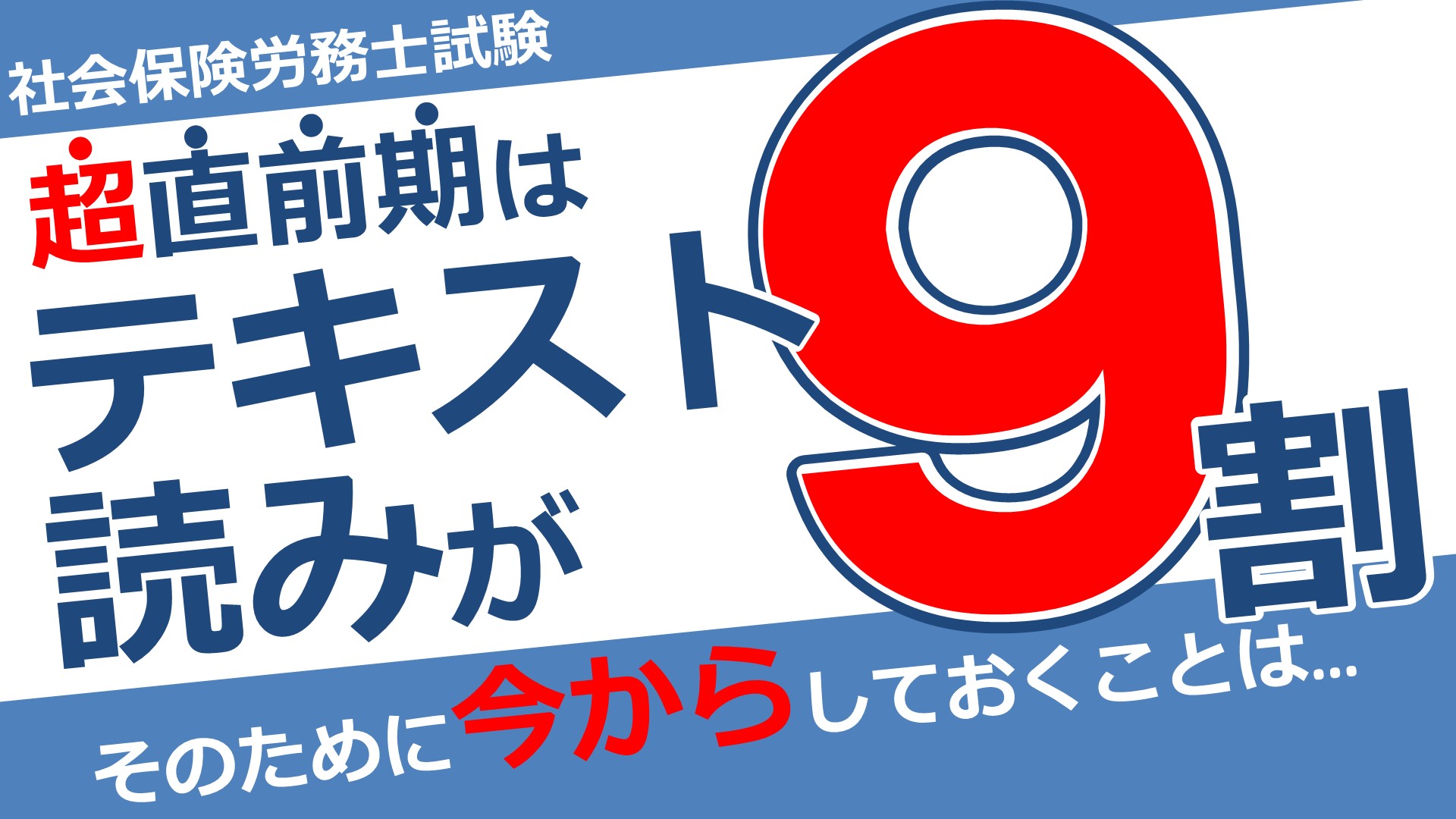皆さんこんにちは。
金沢博憲(社労士24 担当講師)です。
2025年社労士試験に合格された皆様からの合格体験記をご紹介します。
今回は金丸様からお寄せ頂いた体験記です。
誠にありがとうございます。
#社労士24 #経験者合格コース #社労士合格体験記
合格体験記は11月30日までに募集中です。応募フォームは→こちら
プロフィール
40代後半・男性。フルタイムで会社員として勤務。
【社労士を目指したきっかけ】
令和6年1月に、会社の報奨対象だったFP2級に興味を持ち受験し、合格しました。
その上級であるFP1級も検討しましたが、すでにゼネラリスト資格である中小企業診断士を保有していたこと、またコンプライアンス関係業務を担当していたことから、より専門性が高く、労働法も学べる社労士に魅力を感じ、挑戦を決めました。
【得点状況】
令和6年 本試験(1年目)
・選択式:32点(基準点割れなし)
・択一式:40点(健康保険法2点で足切り)
→ 1月末から市販教材のみで独学で学習しました。
令和7年 本試験(2年目・合格年)
・選択式:35点(労一2点)
・択一式:44点(基準点割れなし)
【利用のコンテンツ】
・社労士24+直前対策パック(通信)
・『イラストでわかる労働判例100』(日本法令)
・『よくわかる社労士 合格テキスト 労働に関する一般常識 2025年度版』(TAC市販テキスト)
【学習計画の立て方】
学習記録を厳密にはつけていなかったため細部は曖昧ですが、概ね以下の方針で進めました。
- 社労士24は前年度版の講義動画も視聴できるので、合格年の前年のうちに社会保険科目まで一通り視聴しておきました(特に社会保険科目の理解不足に大きな不安があったためです)。
- 細かい日別計画を立てすぎると計画倒れになりやすいタイプなので、「基礎を徹底する」という基本方針のもと、「テキスト読み」と「トレーニング問題集の反復」を軸にしたシンプルな計画としました。
【勉強時間の作り方】
- 本業での残業が比較的少なかったため、自習室を契約し、平日は退社後に自習室へ直行、週末は朝から自習室にこもるスタイルにしました。
- 通勤時間(往復約2時間)も、動画視聴・テキスト読み・トレーニング問題集(紙版)の解答時間として活用しました。
- 学習時間の外的制約はあまりなかった分、「自分の気力次第」のところが大きく、高熱で会社を休んだ日を除いて、完全に勉強をオフにした日はほぼなかったと思います。
【1日平均の勉強時間とトータルの勉強時間】
- 平日:1日あたり約4時間(通勤時間を含む)
- 土日祝:1日あたり8~10時間※但し、3月までは気分転換のため、毎週土曜は朝から軽登山に行き、夕方から勉強していました。
- 合格年(2年目)のみで少なくとも1,300時間前後、1年目と合計すると2,000時間程度は勉強したと思います。
【回転数】
- 講義視聴:社労士24を全科目で2~3回視聴(少なくともそれ以上は見ていると思います)
- 択一式トレーニング問題集:全科目で7~8回転(但し、労一・社一は各5回転)
- 選択式トレーニング問題集:全科目1~2回転ほど(但し、労一・社一は各4回転)
- テキスト読み:問題集を解きながら頻繁に読み返していたため正確な回数は不明ですが、通し読みだけでも3回は行ったと思います。
【一番苦労したことと解決した方法】
学習内容そのものについては、最初に社労士24を視聴した段階で「究極に無駄がそぎ落とされた神教材だ」と感じて、テキストとトレーニング問題集を素直に繰り返せばスコアが伸びると信じることができたので、あまり苦労した点はなく、日々の勉強はむしろ楽しかったです。
とはいえ、疲れがたまって家族へ愚痴をこぼしてしまい、「そんなに辛いなら勉強なんてやめたら?」と強めに言われてしまったこともありました。
そこで、「勉強できていること自体に感謝する」「家ではできる限り愚痴や弱音を吐かない」と決め、家内安全を図りました。
【選択式の勉強方法】
基本はテキストと択一式の反復で自然と選択式の対応力が高まった、というのが正直なところです。
選択式対策としては、トレ問の労一・社一を4回転しましたが他の科目は1~2回転しかやっていません。
選択式の一般常識対策としては、大原の教材が届くまでの“空白期間”である4月末〜5月初旬頃に、TAC市販の一般常識テキストを購入して3周程度読みました(すべてを覚えきるのは難しいので流し読む感じです。必須ではないと思いますが、選択式の労一・社一への恐怖心を軽減するうえでは有効でした)。
『労働判例100』は毎日3~5事例ずつ読み進める形で、少なくとも3周は回しました。
模試では選択式35点前後を安定的に取れており、「労一・社一以外での足切りはないだろう」という手応えはありましたが、本試験ではその労一が2点でした。
この経験から、選択式はしっかり対策しても、最後は「知っているかどうか」「知らない問題でも類推して正答の選択肢を絞り込めるか」という要素が残る試験制度だと感じています。
そのため、自分にできる努力に全力を尽くしたうえで、最後にはある程度の“運”も必要だと思います。
【不合格だった年の原因と今回変えたこと】
令和6年に不合格だった最大の原因は、1月末からの短期決戦であるにもかかわらず、市販教材を組み合わせて独学で進めてしまい、基本テキストの「参考レベル」に書いてあることまで最初から深掘りしてネットで調べてしまったことだと考えています。
性格的に細かい点が気になりやすく、疑問に思った箇所をネット等で調べているうちに時間を取られ、結果として過去問の択一周回が3周にも届かないまま本試験を迎えてしまいました。
2年目は「基本徹底」と「問題演習の反復」を最重要テーマに据え、インプット教材は労一・社一対策の市販本を除き、社労士24に一本化し、視聴後すぐにトレーニング問題集を解くようにしました。
社労士24のテキストに記載のない内容がトレーニング問題集の解説にあれば、テキストに追記していきました。
学習の終盤には「テキストのどのページのどのあたりに、どの論点が載っているか」がイメージできるようになり、大事な論点をひたすら繰り返すことで記憶が定着していく感覚を得られました。
【勉強内容】
●5月まで(直前期の前)
択一トレーニング問題集の履歴を見ると、5月までに4回転していました。
工夫した点として、間違えた問題や正答できても知識が曖昧だった問題については、解説欄に「何を想起できて、何を想起できなかったのか」を具体的にメモし、次回見直したときに“弱点がわかる”ようにしました。
また、保険科目の横断事項(国民年金の死亡一時金と労災の障害(補償)等年金差額一時金の受給順位の比較など)をテキストや問題集の余白に自分でまとめて書き込むことで、関連論点をまとめて復習できるようにもところどころしました。
●5月~7月(直前期)
受験した模試・演習は以下のとおりです。
-公開模試:クレアール山あて模試、LEC全国公開模試2回、大原公開模試2回
-市販模試:LEC2回、TAC「あてる」1回、TAC「みんなが欲しかった」2回
-大原の直前対策の演習問題
この時期は毎週1本ペースくらいで模試を受験していました。
これらと並行して、1ヶ月に1周のペースで全科目の択一トレーニング問題集を回し、7月末時点で6~7回転に到達していました。
この時期は恐らく月150時間程度の学習となり、かなり追い込んでいたと思います。
●8月(最直前期)
- LECファイナル模試
- LEC公開模試3回目(会場受験は病欠だったため、自宅受験)
- TAC市販「あてる」模試2回目(8月上旬に受験し択一37点。おかげで調子に乗らず、最後まで危機感を持てました)
- 『労働判例100』を毎日3~5事例ずつ読むことを継続
- 択一式トレーニング問題集を全科目1周(労一・社一はやっていません)
- 選択式は、最終週にトレーニング問題集を労一・社一を1周
- 直前対策パックの総合演習の振り返り
- 本試験1週前には、社労士24の全科目を通して再視聴し、知識の最終確認を行いました。
【本試験中に気をつけたこと・感じたこと】
選択式では、労徴・労一・社一で選択肢を絞り切れず、不安を感じていました。特に労一は、一度マークした解答を自分なりの理屈で変更した結果、2点という結果になりました。
「一度決めた解答は根拠なく変えるな」とよく言われますが、私は「迷うということは、何かが引っかかっている証拠」と考え、自分なりに筋の通る理由がイメージできたときは「変える」とあらかじめ決めていました。
今回の労一についても、「あの時点で自分が最善と判断した選択だった」と受け止めています。
択一式は、金沢先生のアドバイスどおり、問題番号の上に「自信あり=□」「曖昧=△」などの印を付けながら解き、見直しをしやすくしました。
ただ、模試では非常に有効でしたが、本試験が難しく、実際には見直しの時間はほとんど取れませんでした。
解く順番は問題冊子どおりとし、健康保険法に入る前に一度トイレに行くと決めていました。前年に健保2点で悔しい思いをしたため、「健保の前に一度、脳を休めてリフレッシュ」したかったからです(そのおかげか、今年は健保で8点を取ることができました)。
実際には雇用保険あたりから手応えのなさに不安がよぎっていましたが、時間配分だけは崩さないよう意識し、悩みすぎずテンポよく解き進めることを心がけました。
一般常識を解き終えた段階で約15分のバッファを確保できたことで、後半も心に多少の余裕を持って取り組めました。
ただし、社会保険3科目とも難しく、とても時間を要してしまい、前述のとおり見直す時間はほとんど取れませんでした。
【受験生の方へのメッセージ】
私は比較的多くの学習時間を確保できたため、環境が異なる方にはそのままは当てはまらない部分もあると思います。
それでも、社労士24は「試験合格に必要なエッセンス」がぎゅっと凝縮された素晴らしい教材であり、これにトレーニング問題集(できれば直前対策パックの演習教材、他校・市販の模試も)の反復を組み合わせることで、合格に必要な実力に確実に近づけると感じました(選択式などに一定の“運”の要素がある試験制度ではありますが、それでも合格レベルまでは確実に導いてくれる教材だと思います)。
社労士24の教材ポテンシャルを信じて、「講義を見る」「テキストを読む」「トレーニング問題集を解く」など、毎日かかさず社労士の勉強に向き合い、愚直に反復徹底していけば、必ず問題を解く力を養えるはずです。
金沢先生の門下生として、来年、皆さまが社労士24で合格を勝ち取られることを心よりお祈りしています。
【その他ご感想など】
社労士24という素晴らしい教材を作り上げてくださった金沢先生には、感謝の気持ちしかありません。
Xでのポストにも何度も励まされました。本当にありがとうございました。
その他の合格体験記
その他の合格体験記は下記のリンク先でご覧いただけます。
過去にお寄せ頂いた合格体験記です。 2024年対策
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24