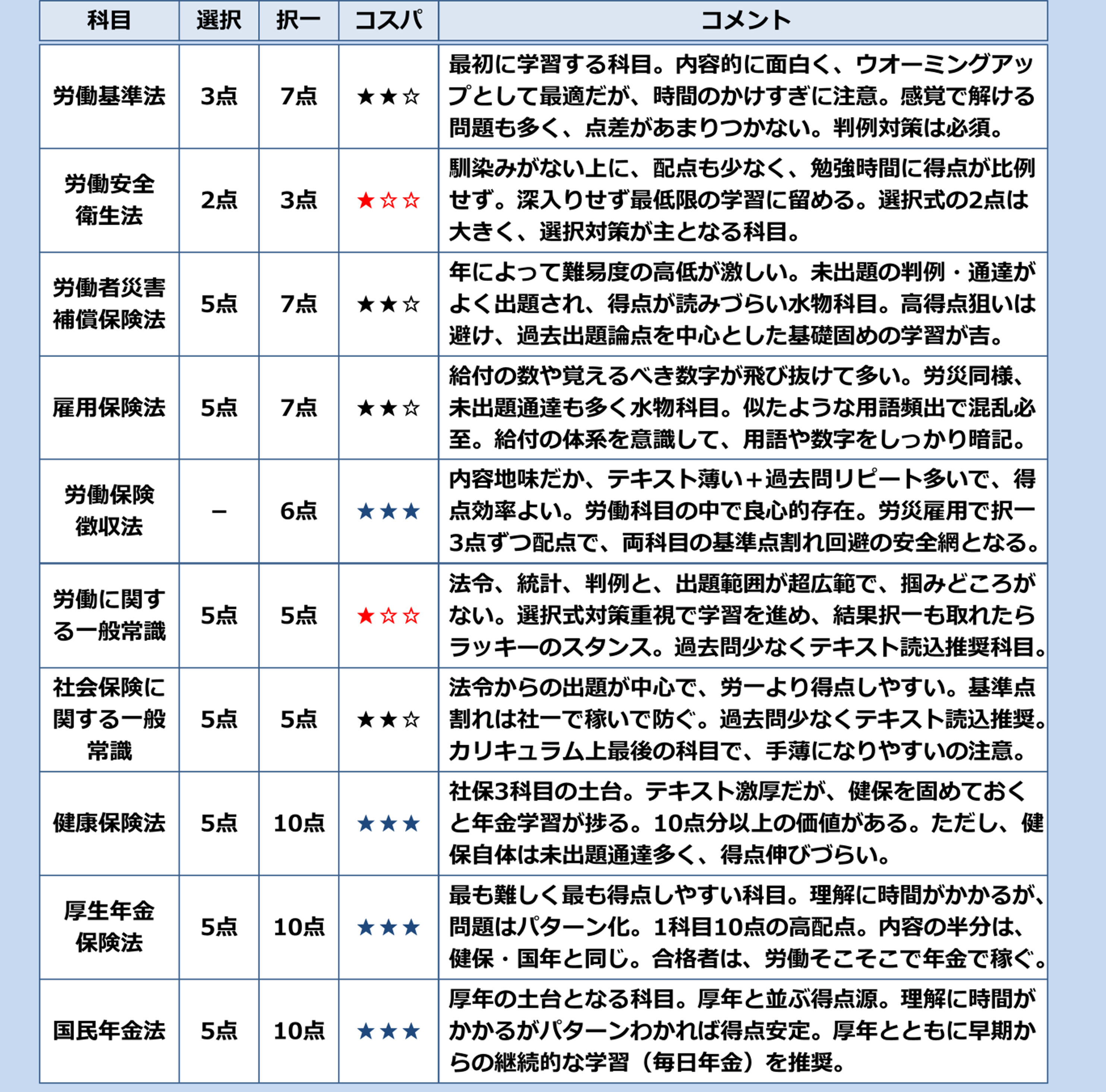皆さんこんにちは。
金沢博憲(社労士24 担当講師)です。
2025年社労士試験に合格された皆様からの合格体験記をご紹介します。
今回はななな様からお寄せ頂いた体験記です。
誠にありがとうございます。
#社労士24 #経験者合格コース #社労士合格体験記
合格体験記は11月30日までに募集中です。応募フォームは→こちら
プロフィール
30代前半 女性
地方公務員(社労士試験関係では、介護保険課にて2年勤務経験あり)
5歳、1歳の子有り 育休中
【社労士を目指したきっかけ】
今後の育児と仕事の両立について考えたときに、転職が頭に浮かびました。
しかし、特にこれといったスキルがなかったため、まずは何か資格を取得しようと考えました。
初めは、普段の業務で聞いた事のあった行政書士に興味を持ちましたが、独立して働く人が多い職業のようで、自分には合わないと思いました。
そういった中、大原のホームページを見ていて、行政書士と並んで書いてあった社会保険労務士という資格が目に留まりました。
「資格の活かし方が色々ありそう。内容もなんだか面白そう。しかも全問マークシート!」と思ったことが勉強を始めたきっかけです。
また、転職しないことになったとしても、学習内容が今後の公務員人生で活かせられそうだと感じたことも理由の一つです。
【得点状況】
初受験です
選択式 4/4/5/2/3/4/5/5 計32点
択一式 7/5/3/6/8/7/9 計45点
【利用のコンテンツ】
社労士合格コース(通信)
社労士24
金沢先生のメルマガ、YouTube、X、ブログ
秒トレ
イラストでわかる労働判例100 第2版 (5月〜追加)
【学習計画の立て方】
教材に同封されている学習計画表から遅れないことを意識していました。
講義を一度に視聴するのは時間の面でも集中力の面でも難しかったので、2~3日に分けていました。
講義が終わった後(直前期)は、金沢先生のブログ通り6、7月はひと月で全科目1周、8月は2週間で全科目1周、その後1週間で全科目1周ができるように自分なりにスケジュールを組んで取り組みました。
【勉強時間の作り方】
主人が不規則な勤務、かつ、仕事の疲れからか家にいても寝てしまっていることが多かったので、平日も土日もワンオペでした。
特に合格コースの講義が週2となった年明けからは勉強時間の捻出が大変でした。
解決方法としては、スキマ時間の活用と、なにより気合いです。(あまり参考にならないですね…)
具体的には、子どもが寝てる間はほぼ全て勉強に充てました。
年明けからは上の子を保育園に送ったあと、下の子にはひとり遊びしてもらい、その時間も勉強に充てました。
自分の体調が悪くない限りは上記の通りスケジュールを守っていたため、遅れそうになったら、寝た下の子を抱っこしたまま講義を聞いたり、寝かしつけで一緒に寝てしまったときは、授乳で起こされた夜中2時3時から択一を解くこともありました。
特に8月の試験日前ラスト1週は、石戸先生がXでポストされていた「ここからは気力がすべて!」にパワーをもらい、夜中抱っこ紐で寝かしつけながらテキスト読みを行いました。
保育園の送迎(徒歩)と、寝かしつけをしているのに上の子が騒ぐ虚無時間は社労士24や金沢先生のYouTubeを聞きました。
社労士24導入前は、寝かしつけ時に時間がかかると、勉強出来ないことに対して焦りや苛立ちが出てしまっていました。
しかし、社労士24導入後は、スキマ時間を活用して勉強していると意識を変えることができたので、メンタル面で非常に支えになりました。
【1日平均の勉強時間とトータルの勉強時間】
・年明け前(講義週1)
平日 2時間 休日 1時間
・年明け後(講義週2)
平日 3〜4時間 休日 2〜3時間
・8月
平日 4〜6時間 休日 4時間
計890時間(上記の耳勉の時間もほぼ含めています)
【回転数】
・社労士24:合格コースの講義後に1回転、直前期に苦手なところを+1〜2回転
+年明け前に昨年度の健保〜厚年を1回転
・合格コースのテキスト:5〜8周
・択一式:4〜9周(年金2科目は4〜10周)
・選択式:1〜3周(労一は2〜5周)
【一番苦労したことと解決した方法】
労基法が苦手だったことです。
どう勉強するべきか掴めないまま講義が終了してしまったからか、私の社会人としての常識が欠損しているからなのか(勉強を始めた10月、36協定って何?というレベル)、ずっと馴染むことが出来ませんでした。
対策としては、接触機会を増やしました。
勉強当初から苦手意識があったため、他の労働科目よりも社労士24、テキスト、択トレの回転数を増やしました。
労働科目中間テストでも直前対策でも労基が足を引っ張り続けていて、試験までに克服できるのかという不安がありましたが、「こんなにずっとやってるのだから、きっと大丈夫」と自己暗示をかけ、学習を続けました。
今となっては、他の教材に浮気せず、大原の教材を信じ抜いたことが結果に表れたと感じます。
【選択式の勉強方法】
前述の通り、選択式トレーニング問題集も回転するようにしました。
テキストに記載のない問題、テキストで参考となっている問題は問題集にその旨を記入し、テキスト記載の問題を重点的に解くようにしていました。
また、統計白書対策に関しては、テキスト折り込みの問題があったので、それを3回転しました。
こちらは選トレとは対策を変え、テキストに記載のない問題も解き、答えをテキストに書き加えて、薄く広く知識を得るようにしていました。
【勉強内容】
まずは、確認テストと模試の結果を記憶の範囲で紹介します。
(過年度の合格体験記で載せていらっしゃった方がいて、目標として参考になったので記入いたします)
確認テスト
労基安衛 17点、労災雇用 15点、徴収労一 19点、労働中間 26点
健保 20点、国年 20点、厚年 18点、社一 19点、社保中間 24点
直前対策 労働①15点 ②20点 ③19点 社保①19点 ②20点 ③20点
第1回模試:総合評価Cランク(選択Aランク、択一39点Cランク)
第2回模試:総合評価Bランク(選択Aランク、択一46点Bランク健保割れ)
・5月まで(直前期の前)
大原カリキュラム通りに進めました。
試行錯誤した時期が長かったですが、労一あたりから、
講義→
視聴直後に択トレ1周目、該当箇所の社労士24視聴→
次の日に2週目とテキスト読み→
その日の午後か次の日に3週目&選トレ→
次の日に間違えのみ4週目→次の講義…
のルーティンで確認テストでは安定して高得点が取れるようになりました。
確認テストの前までには、頭の中でごちゃついている部分をまとめた付箋を都度作成していました。
また、情報収集をしていると年金科目の早期習得が重要であると感じました。
そのため、11月〜12月に社労士24で昨年度の健保〜厚年を視聴しました。
また、フリマサイトで購入した過年度の択トレも解きました。
正直それが直接知識に繋がったわけではないのですが、苦手意識を持たず年金科目に突入できました。
・5月~7月(直前期)
5月は通常講義、6月は直前対策の講義を受けつつ全科目択トレ1周、7月は全科目テキスト読みと択トレを行いました。
また、金沢先生のXで#神まとめ として過去に投稿されていた、労災と雇用の給付概要一覧を印刷し(雇用は法改正部分を自分で書き加え)、冷蔵庫に貼り、ふとしたときに眺めるようにしていました。
さらに、本試験前まで継続して、今まで手が回らなかった毎日年金、毎日目的条文、毎日判例を行うように心がけました(できない日もありました)。
1回目の全統模試で間違えた問題を分析したところ、これまでに付箋でまとめていたのに覚えきれず失点した問題がかなりの数ありました。
そこで、2回目の模試へ向けて付箋の暗記をする時間を取りました。その結果、2回目の模試では点数がアップしました。
このことから、本試験に向けて、付箋を含めたまとめノートを作るようにしました。
・8月(最直前期)
初めの2週間は毎日1科目ずつテキスト読みを行い、それとは別の科目(テキスト読みが労働科目なら社保科目)の選トレを行いました。
次の1週間は模試で点数が低かった科目を中心にテキスト読み、それとは別の科目の過去の確認テスト、中間テスト、択一演習、択トレに付箋をつけた問題を解き直しました。
最後の1週間はテキスト読み、別の科目の模試の解き直しを行いました。
択一の問題を解く感覚が鈍るのが怖かったので、毎日問題を解くようにしていました。
【本試験中に気をつけたこと・感じたこと】
気をつけたことは、時間配分、解く順番、根拠なく選択肢を変えないことです。
時間配分、解く順番については金沢先生のブログを参考に、1科目25分、選択式も択一式も年金科目から解きました。
また、金沢先生のYouTubeで、択一式の1問目はこねくり回した問題が出やすいとおっしゃっていたことを参考に、問10からさかのぼって解くようにしていました。(その方が解きやすい問題に当たる可能性が高く、問題を解くリズムを作りやすいのではないか?と考えたため。)
さらに、模試でマークミスをしてしまった経験から、選んだ選択肢とマークが合っているか、マークの色は薄くないか、重複してマークしてしまっていないか等マークミスのチェックは入念に行いました。
【受験生の方へのメッセージ】
1年で合格できるとは考えておらず、本当に運が良かったなとしか思えないのですが、当初から意識していたのは、大原の確認テストと中間テストでいい点数を取ることです。どちらも9割目標で勉強していました。
テストになんとか食らいつくことで、1年で合格できる知識を身につけられた気がします。
【その他ご感想など】
初学にもかかわらず私が合格できたのは、100%間違いなく、社労士24があったからです。
スキマ時間の活用、それによるメンタル面での支え、覚えやすい語呂合わせ、苦手な部分のみ短時間で復習可能なカリキュラムが最高でした。
(余談ですが、よく合格された方が「最後の方は〇倍速で聴いていました」などとおっしゃる中で、私は直前期でも0.9倍速が限界でした。)
金沢先生の各種コンテンツも最大限活用させていただきました。
本当にありがとうございました。
その他の合格体験記
その他の合格体験記は下記のリンク先でご覧いただけます。
過去にお寄せ頂いた合格体験記です。 2024年対策
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24